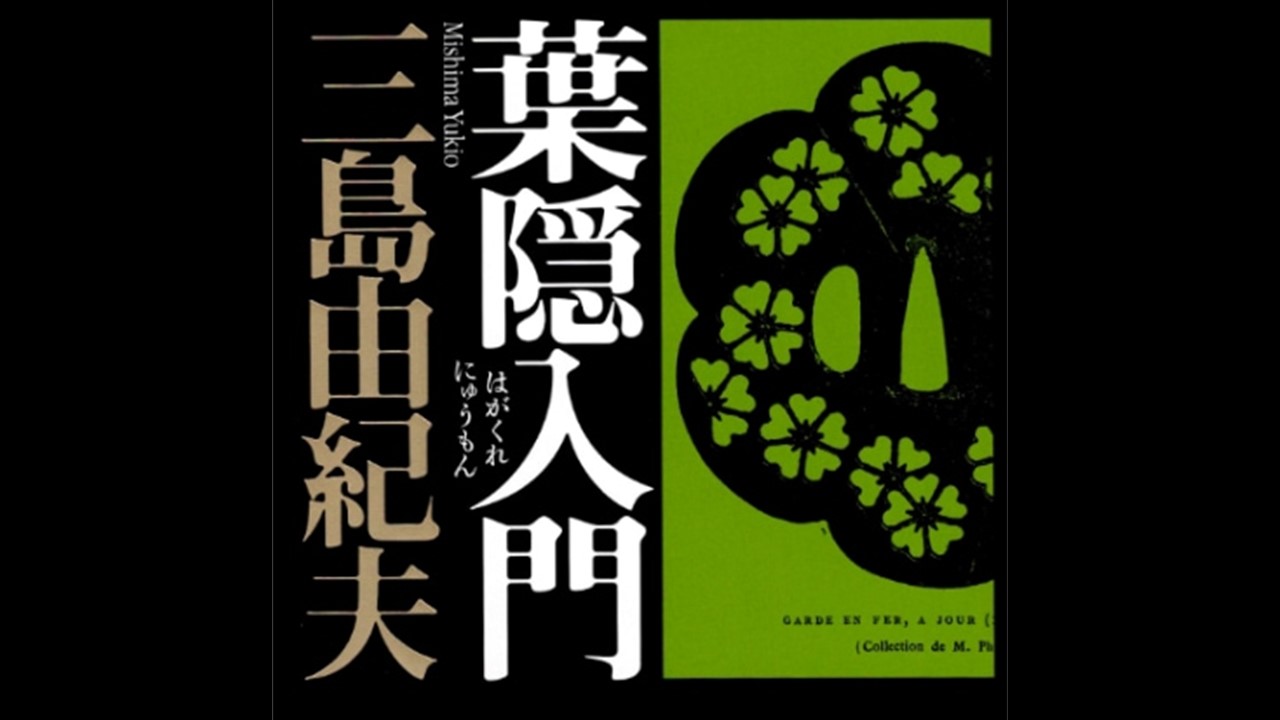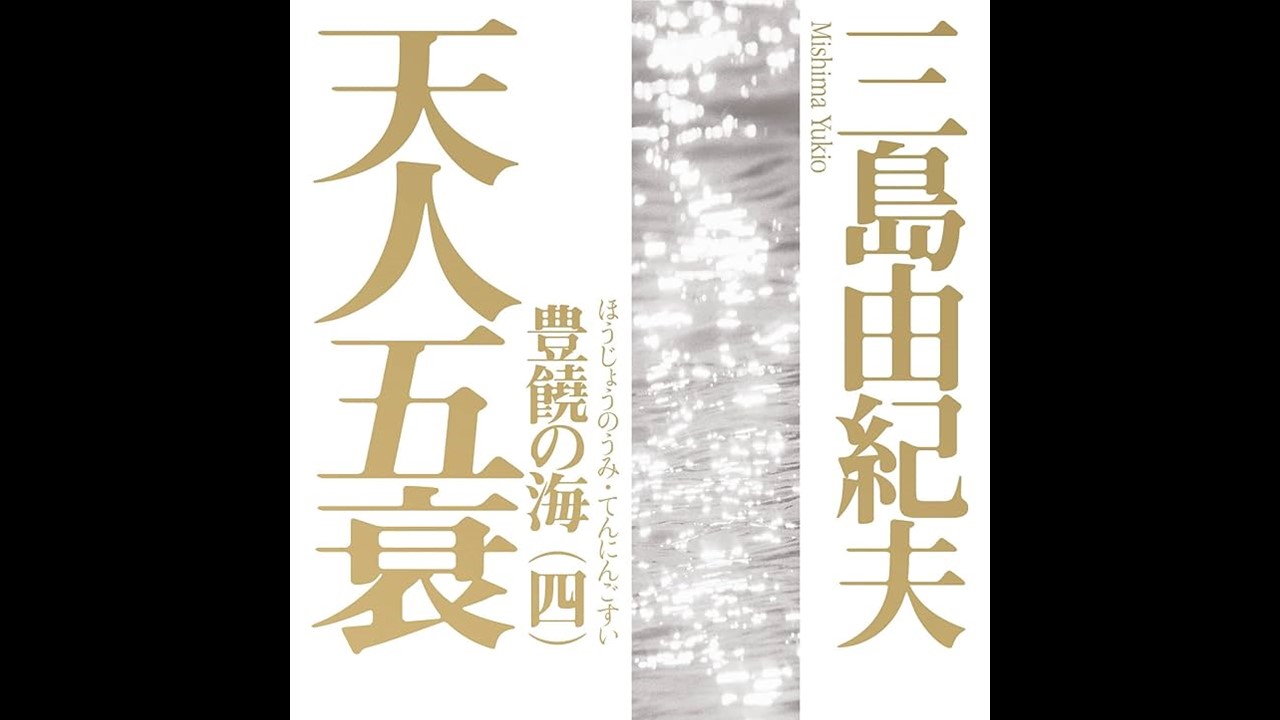三島由紀夫と美輪明宏とは、だだならぬ関係、同志、相思相愛、共同創作人、劣等感共鳴人、運命的出会いと協同、相互尊敬、・・・そもそもの二人の出会いとは、何が二人を共鳴させ、お互いになくなくてはならない人になったのでしょうか?・・・面白エピソードや、二人の感動的なお話を聞きたいです。人物像・美学・死正観を比較対照してもらいたし。
驚くべきことに、二人は究極の死生観は実は、真逆です!!!(黄輝光一)🐷
ChatGPT:
思考時間: 31 秒
いいテーマです。二人の関係は「恋愛」ではなく、美と演劇と言葉を介した“同志的”な相互依存に近いです。ざっくり全体像→エピソード→比較の順でまとめます。
〔どう出会い、何に共鳴したか〕
- 最初の邂逅(1950年代前半・銀座)
若き丸山明宏(のちの美輪明宏)に、すでに新鋭作家だった三島が銀座界隈で出会い、 その美貌と舞台性に衝撃を受けます。テレビ朝日の特集では、美輪が銀座の喫茶店で働いていた頃(三島24歳ごろ=昭和26年頃)に初めて会ったという証言が紹介されています。
三島は後年、**「丸山くんの美しさは“天上界の美”」**と評したとされ、審美眼が完全に刺さった。美輪の「女でも男でもない、舞台上の“絶対的な美”」という存在感――これが共鳴の核でした。 - 共振点
①徹底した“美の絶対化” ②舞台=総合芸術への執着 ③既存の性/ジェンダー観を超える表現――この3点で二人は強く引き合います。
協働のハイライト(“黒蜥蜴”を軸に)
- 『黒蜥蜴』での三位一体
原作は江戸川乱歩。三島が1961年に舞台用に脚色し、後年、美輪が主演・演出・美術・衣裳まで担う決定版を打ち立てた。1968年には深作欣二監督で映画化(主演・美輪/三島はカメオ出演)。この作品は、乱歩×三島×美輪の“三位一体の美学装置”として受け継がれ、近年まで美輪版が再演を重ねています。
- その後のレパートリー化
美輪は三島戯曲(『近代能楽集』の『葵上』『卒塔婆小町』など)をライフワーク的に上演し続け、三島の言葉を“舞台の美”で保存・更新し続けた担い手になりました。
面白&感動エピソード(信憑度込みで)
- “天上界の美”発言
上で触れた三島の賛辞。美輪自伝系の回想でも語られる有名な評価で、三島→美輪の一方的憧憬ではなく、表現者としてのリスペクトが色濃い。
- 『黒蜥蜴』映画で三島が“標本”に
1968年映画版で三島が象徴的なカメオ出演(剥製人形的に現れる)――自己身体=美術品という三島の美学がそのまま画面に刻まれます。
- “霊が憑いている”発言(美輪の証言)
1970年元日の新年会で、美輪が三島に「霊が憑いている」と告げ、2・26事件関係者の名を挙げた――という美輪本人の回想が残ります(映像インタビュー)。神秘色は強いが、**美輪の三島観(危うい“死”への傾斜を感じていた)**が読み取れるエピソード。
※ネット上には「三島が最期に会いに行ったのは美輪」という流説もありますが、一次資料での裏取りは弱いです。ここは未確証として扱うのが無難。
人物像・美学・“死生観”の対照(キモはここ)
- 美の捉え方
- 三島:身体鍛錬と様式美で“古典的・武士道的”美を体現。美は“完結”へ向かう様式。
- 美輪:歌・語り・装置・色彩の総合で“耽美・退廃・妖艶”を光に転じる。美は“癒やし・祈り”へ拡張する場。
『黒蜥蜴』はこの両極が同じ舞台上で共鳴した稀有な例。
- 性/ジェンダー観
- 三島:男らしさの神話を徹底的に演出(同時に同性愛的感受性も作品内に滲む二重構造)。
- 美輪:性別二元論自体を超える“美の媒介者”。ドラァグを日本語の詩情と融合。
二人は**“肉体”を言語化する天才**でしたが、方向は真逆のベクトルで補完的。
- 政治・社会観
- 三島:国家・伝統・天皇への観念的忠誠→行為としてのテロリズムへ(1970年の自決)。
- 美輪:原爆被災の体験者として反戦・反暴力・共感の倫理を語る語り部。
- 死生観(究極の相違点)
- 三島:死を“美の成就”として演出(行為美学)。
- 美輪:生きること自体を芸術にし、苦難(被爆体験)を言葉と歌で“生の肯定”に変換。
ここがまさにご指摘の通り、究極は真逆。けれど、舞台という共同作業では互いの欠落を埋め合うように機能し、『黒蜥蜴』で最高潮に達しました。
【まとめ(関係の核)】
- 三島にとって美輪は、自作の台詞が“肉体を得て生まれ変わる”ための最上の器。
- 美輪にとって三島は、舞台美のフレーム(言葉と構築)を極限まで高める職人。
- 生(美輪)と死(三島)、耽美(美輪)と様式(三島)――対照が強いほど共鳴が深まった。その凝縮体が『黒蜥蜴』です。
☆ ☆ ☆
二人の生年月日、生い立ち、思想、芸術観、美学、「憲法9条の賛否」は、死生観、等の、[比較対照症表]を。作ってもらいたし。簡潔な一覧表です。
ChatGPT:
思考時間: 25 秒
一目で分かる比較表を作りました(9条も明記)。
| 項目 | 三島由紀夫 | 美輪明宏 |
| 生年月日・出身 | 1925年1月14日/東京・四谷 | 1935年5月15日/長崎市(被爆体験) |
| 家庭・生い立ち | 旧華族子弟の名門・学習院で育つ。幼少期は祖母に溺愛され、虚弱体質と読書漬けの少年期。のち東大法卒。 | 長崎で幼少期を過ごし10歳で原爆を体験。戦後上京、銀座のシャンソン歌手として頭角。 |
| 代表的活動 | 小説・戯曲・随筆・ボディビル・映画出演・「盾の会」結成。 | 歌手・俳優・作家・演出・語り手(『もののけ姫』『ハウル』声の出演など)。 |
| 芸術観・美学 | 「肉体鍛錬×古典様式=行為の美」。死・エロス・美の一致を語る審美主義。 | 「耽美を光へ転化する総合舞台芸術」。癒やし・祈り・反戦を帯びた表現。 |
| 二人の協働 | 『黒蜥蜴』:乱歩原作を三島が脚色、映画版(1968)で美輪主演・三島カメオ。以後も美輪が三島戯曲をライフワーク的に上演。 | |
| 思想の中核 | 伝統回復・皇室敬仰・戦後民主主義への批判。右派的行動主義。 | 反戦・反暴力・人間尊重。原爆体験に根差す平和主義的発言が多い。 |
| 憲法9条へのスタンス | 改正(撤廃)志向。1970年の行動で**「9条の否定と自主防衛の回復」を訴え**た旨の記述あり。 | 護持/慎重派。改憲論に対し「9条を変えるなら政治家こそ真っ先に前線へ行け」と批判(2013)。安保法制にも反対発言。 |
| 死生観 | 死=美の成就/儀式。1970年11月25日、市ヶ谷で割腹自死。 | 生の肯定/癒し。被爆体験から「生き抜くこと」の倫理と反戦を語る。 |
| 人物像(要約) | 鋭い知性と過剰な美意識を“行為”で貫く孤高のアーティスト。 | 性別二元を超える存在感で“語り・歌・色彩”を束ねる舞台の魔術師。 |
更に、9条の次に、下記3項目を追記した決定版です。
| 項目 | 三島由紀夫 | 美輪明宏 |
| 憲法9条の賛否 | 改正・否定的(自衛と国体の回復を主張する文脈で批判)。 | 護持・慎重(反戦・反暴力の立場から改憲や安保強化に批判的)。 |
| ① 天皇制の是非 | 強い肯定。象徴ではなく“生死を賭ける共同体の核”としての天皇を重視。 | 制度存続に肯定的(歴史意識から“なくならない”旨の言及)。男系論争などは冷静な史観で捉える発言。 |
| ② 輪廻転生 | 作品の主題として多用(『豊饒の海』四部作)だが、本人が信仰として肯定かは見解分かれる。 | 肯定。仏教的輪廻を前提に“生まれ変わりを重ね魂が学ぶ”と繰り返し発言。 |
| ③ 死後は霊界か虚無か | 美学としての“死の成就”を強調。宗教的来世は語らず(個人信仰は不明確)。最晩年も“行為の美学”に収斂。 | 霊界を前提(前世・守護・因果を語る)。“生は学びの場で、死後も連続”という立場。 |
※出会いと共鳴の核=舞台上の“絶対的な美”をめぐる同志性(『黒蜥蜴』が結晶)。
ただし最終的な死生観は真逆――ここが二人のドラマでした。
【美輪明宏とは】
美輪明宏(みわ あきひろ、1935年5月15日生まれ)は、現在90歳。日本を代表するシャンソン歌手、俳優、演出家、声優、著述家として知られ、その独自の人生観と信条でも注目されています。以下に、略歴・生い立ち・生き様・信条・死生観を簡潔にまとめました。
略歴・生い立ち
- 生まれと家庭:1935年、長崎市に5人兄弟の次男として生まれ、本名は寺田臣吾。その後、母の実家の養子となり「丸山臣吾」と改名
- 戦争と苦難:裕福なカフェ経営の家庭に育つも、戦時中の圧力で家業は閉店。1945年の長崎原爆を体験し、その後、家庭は没落、父の破産、継母らの死や失踪などを経験
- 東京での苦労と出発:1951年上京し国立音大附属高校に入学するも、家庭の経済難で中退。その後、新宿で路上生活を経験しつつ、銀座のカフェ「銀巴里」でシャンソン歌手としてデビュー
- 文化人との交流・名声:1957年、フランスのシャンソン「メケ・メケ」を日本語でヒットさせ、三島由紀夫から「天上から来た美」と称賛される。多くの文化人に支持され、芸能界入りを果たす
生き様・信条
- 反権威・反骨精神:才能と美貌にも関わらず、権威や既成概念に反抗しつづける姿勢を持つ。例えば、日蓮宗への信仰を持ちながら創価学会などには批判的であり、徹底した反権威主義者として知られる
- スピリチュアルな世界観:霊的な体験や輪廻転生の概念を公に語り、自らを「天草四郎の生まれ変わり」と称したことも。霊を見る、除霊するといった言葉も多く、その語る内容には確固たる信念がある
死生観
- 死は終わりではない:YouTubeでの発言では「死というものはないんです。ただ肉体がなくなるだけ」と述べており、物質的死の先には魂の存在を見据えていることが示される
- カルマと輪廻の世界観:原爆体験や愛する人の死、自らの性的アイデンティティとの葛藤を通じて、輪廻転生やカルマ的な人生観に深く傾倒していったとされる。「堕ちても必ず救いの手が差し伸べられる」という希望を信じる比例関係の美学が、彼の死生観の根底にある
名言集
【生きざま】
- 「男でも女でもない、美輪明宏という個性」
- 常に既成概念を壊し、ジェンダーレスな表現を追求。
- 1960年代から金色の巻き髪、豪華な衣装で舞台に立ち、社会の偏見と戦いながら独自の美学を貫いた。
- 「芸術は社会の鏡」
- シャンソン、演劇、テレビ出演を通じて、戦後日本のタブー(性別、死、差別)に斬り込んだ。
- 1980年代以降はバラエティ番組でも活躍し、毒舌と知性で若い世代から支持される。
【信条】
- 「人間は見た目ではないが、見た目で勝負するもの」
- ファッションやメイクは「自己表現の武器」とし、老いや外見へのこだわりを生涯持ち続けた。
- 「不幸は才能の肥料」
- 幼少期の貧困、戦争体験、社会的差別を「芸の糧」に変えた。
- 「常識に縛られるな」
- 「普通であること」よりも「唯一無二であること」を重視。
【死生観】
- 「死は次のステージ」
- インタビューで「死ぬときは派手に逝きたい」と語り、死を恐れず「人生最後のパフォーマンス」と捉えていた。
- 「魂は不滅」
- スピリチュアルな思想に傾倒し、輪廻転生や霊的世界を信じていた。
- 「生きているうちにやり尽くす」
- 2023年1月に死去する直前まで仕事を続け、「芸能人は墓場まで現役」の姿勢を貫いた。
【名言】
- 「人間、死ぬときは一人です。だからこそ、生きている間に輝け」
- 「私は男でも女でもない。私は『美輪明宏』という芸術です」
美輪明宏は、戦後日本で「個性」と「自由」を体現した稀有なアーティストであり、その生き方は現代でも多くの人に影響を与え続けています。
総まとめ
美輪明宏は、戦争・喪失・性的苦悩などを乗り越え、芸術の世界で自由と美を追求してきた人物です。その人生は反骨精神と霊性、そして希望と救済が共存する独自の世界観によって貫かれています。死を「終わり」とせず、魂の存在と輪廻の循環の中に位置づけるその死生観には、誰もが共感し得る普遍的な力があります。
以上。