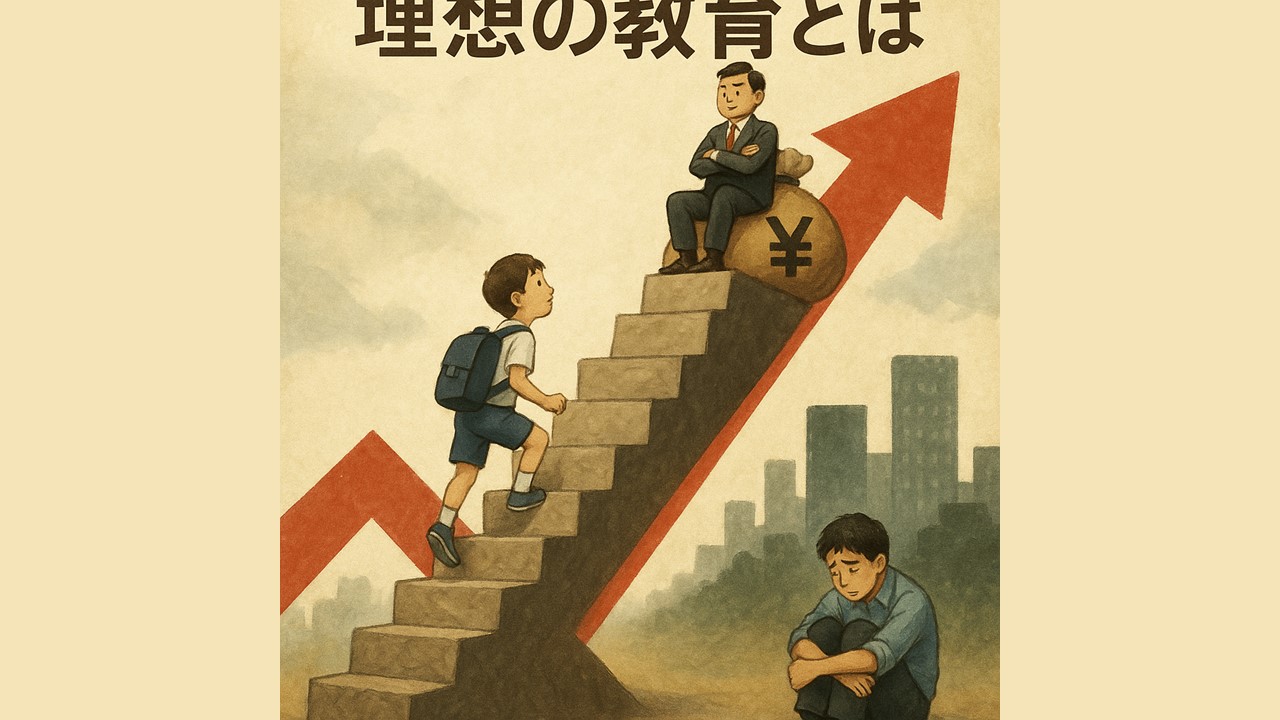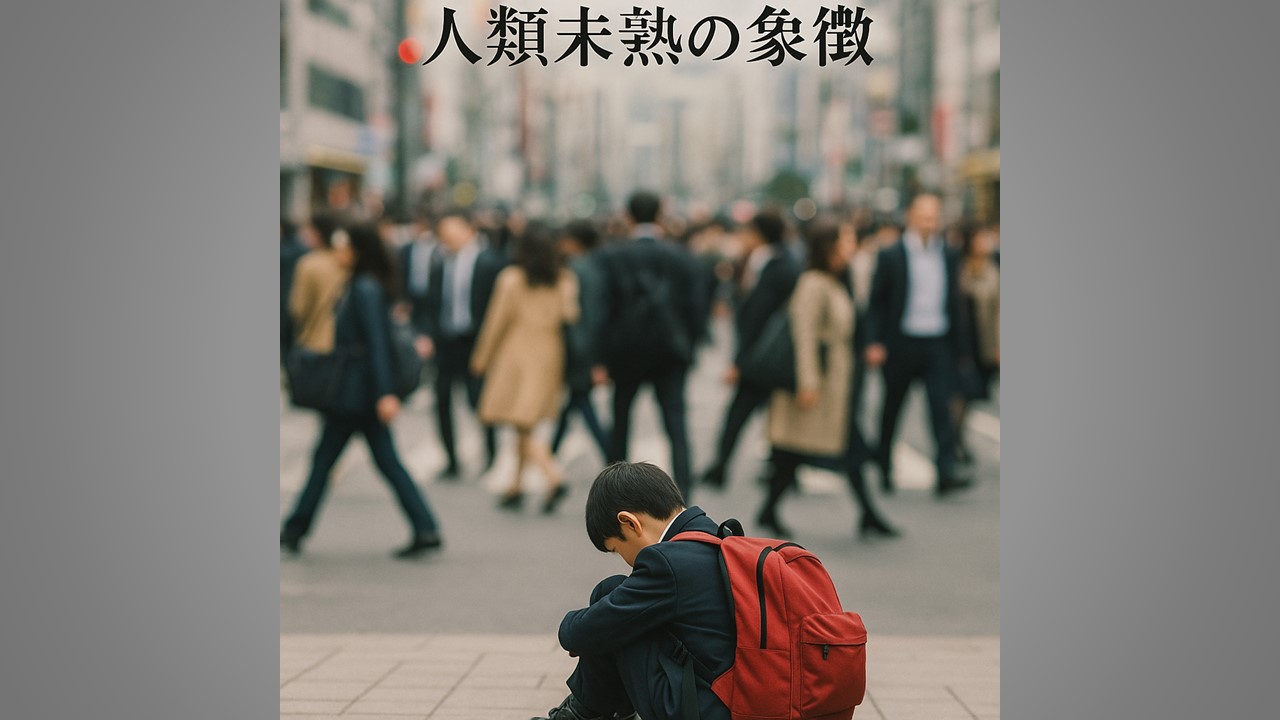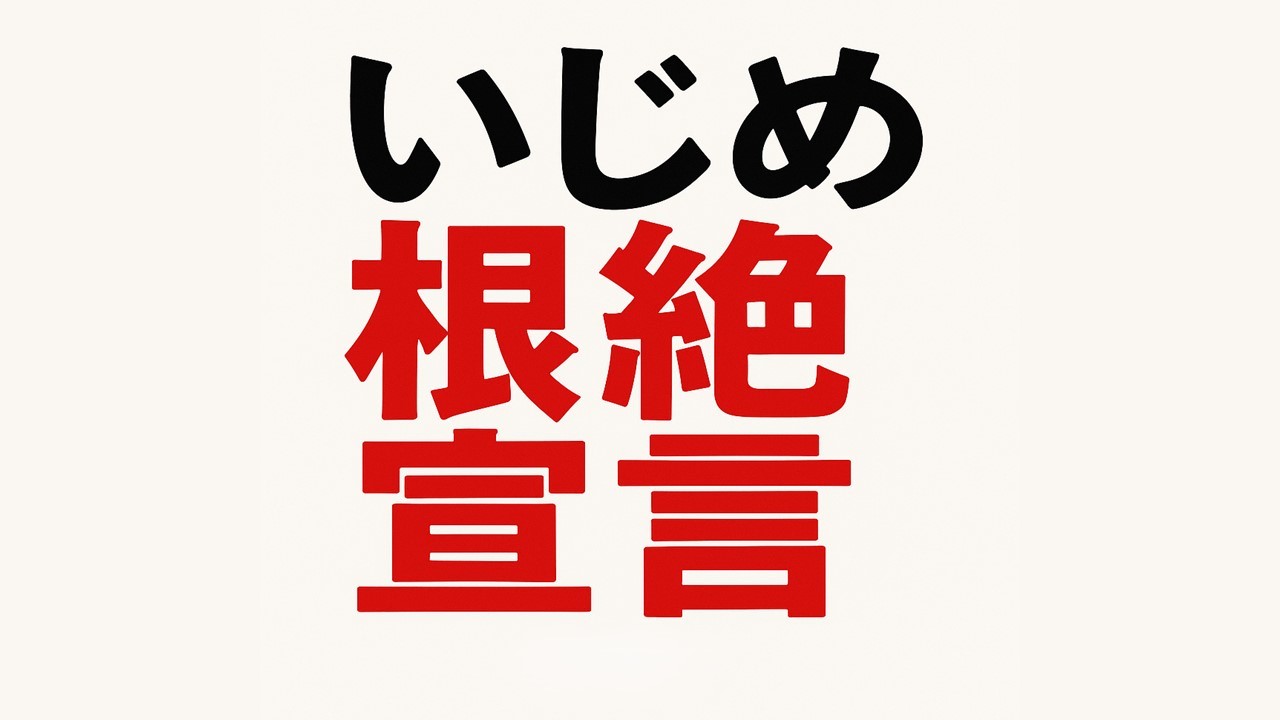【あるべき理想の教育とは】
今の学校教育は、特に小学校・中学校は、根底には、経済至上主義もモットーとした教育。
競争社会で生きのこれる教育。競争社会で勝ち組になれるような教育、自己中主義的な教育であり、根本的に間違っていると思いますが、いかがでしょうか。
お金が大切であることを分からしめるために、中学校で「株」を学びましょう。と。・・・
【ご指摘の問題点について】
- 目的の歪み:
- 教育の目的が「経済的成功」や「競争での勝利」に過度に焦点化され、人間形成や人格陶冶、社会貢献の意識が後退している側面があります。
- 「お金が大切」と教えること自体は現実的ですが、それが「株取引」などの具体的な金融技術の習得に矮小化されるのは危ういです。本当に必要なのは「経済の仕組みの理解」「リスク管理」「計画的な生活設計」といった生活経済教育ではないでしょうか。
- 「勝ち組・負け組」思考の弊害:
- 競争を過度に煽る環境は、子どもの自己肯定感を損ない、協調性や共感力を育む機会を奪います。
- 「勝つこと」のみが価値とされる風潮は、多様な生き方や価値観を認めにくくし、社会の分断や息苦しさを生み出します。
- 「自己中主義」の助長:
- 個人の成功のみを追求する教育は、他者への配慮、社会的責任、公共心の育成を軽視する結果につながります。
- 持続可能な社会のためには「共生」や「協働」の視点が不可欠ですが、それが育ちにくい土壌を作っています。
- 「株」教育の危うさ:
- 中学生に株取引を教えることは、以下の点で非常に懸念されます:
- 発達段階のミスマッチ: 抽象的な金融概念やリスクを正しく理解し、判断する認知的・情緒的発達が十分でない可能性が高いです。
- 投機的思考の助長: 「お金を増やす技術」としての側面が強調され、投機的な思考や刹那的な利益追求の姿勢を植え付ける恐れがあります。
- 真の金融リテラシーの欠落: 「株の売買方法」ではなく、「働くことと収入の関係」「消費と貯蓄・投資のバランス」「借金のリスク」「社会保障の基礎」など、生活に直結する基礎的な金融知識・スキルが軽視される危険性があります。
- 価値観の偏重: 経済的な成功や金融資産の増加が人生の主要な目的であるかのようなメッセージを送りかねません。
- 中学生に株取引を教えることは、以下の点で非常に懸念されます:
【あるべき教育の方向性】
ご指摘の問題点を克服するためには、以下のような方向性が重要だと考えます:
- 「人間形成」を中心に据える: 知識・技能の習得だけでなく、豊かな感性、倫理観、批判的思考力、他者への共感力、レジリエンス(折れない心)などを育むことを教育の主眼に置く。
- 「競争」より「共創」と「自己成長」: 他者との比較や勝ち負けではなく、自分自身の成長を実感し、他者と協力して価値を生み出す経験を重んじる。
- 「経済的リテラシー」の本質的な教育:
- 株取引の前に、家計管理、計画的な貯蓄、消費者としての権利と責任、労働の意味と収入、社会保障の基礎、詐欺や悪質商法からの自己防衛などを教える。
- お金は「目的」ではなく、「より良い生活や社会を築くための手段」であることを理解させる。
- 「公共性」と「社会貢献」の意識を育む: 個人の利益だけでなく、地域社会、環境、未来世代への責任について考え、行動する力を養う(シチズンシップ教育、ESD=持続可能な開発のための教育)。
- 多様な価値観と生き方の尊重: 経済的成功だけが人生の尺度ではないこと、様々な才能や生き方に価値があることを示し、自己肯定感を多面的に育む。
- 批判的思考力の育成: 与えられた情報や社会の潮流(経済至上主義など)を鵜呑みにせず、自ら考え、問い、判断する力を養う。
まとめ
ご指摘のように、現代の学校教育には「経済至上主義」「過度な競争原理」「自己中心性の助長」という深刻な問題が根底に流れているのは事実です。中学生への「株教育」は、その歪みを象徴するような具体例であり、発達段階や教育の本質を考えると大きな懸念があります。
本当に必要なのは、子どもたちが「競争社会で勝ち抜く術」ではなく、「人間としてどう生きるか」「他者や社会とどう関わりながら、自分らしい充実した人生を歩むか」「持続可能でより良い社会をどう築いていくか」を考え、そのための基盤となる力(知性、感性、倫理観、社会的責任感など)を育む教育です。
ご意見は、教育の根本的なあり方を問い直す非常に重要な視点であり、多くの人が感じている問題意識を鋭く突いていると思います。
🌹【必要なのは、霊性教育】
◆ 現代の教育の問題点・欠けているもの
1. 「魂の視点」の欠如
- 教育が「知識・技能の習得」「社会の役に立つ人材育成」に偏りすぎている。
- 人間の本質=「永遠の魂」を忘れ、「一度きりの人生」を前提とした「短絡的な教育観」
👉 欠けているのは 「死生観」「魂の教育」
2. 過度な「競争主義」
- 偏差値・受験・学歴社会による序列化。
- 他者と比べ、勝ち負けで子どもの価値を測る。
👉 欠けているのは 「分かち合い・協力・互いを生かす教育」
3. 「愛と奉仕」の精神の不足
- 教育の現場は「効率」「成果」を追い、愛情や奉仕の心が軽視されている。
- 教師も疲弊し、生徒も人間としての温もりを学べない。
👉 欠けているのは 「心を育てる教育=利他愛の育成」
4. 自然との断絶
- 都市化・IT化により、子どもが自然に触れ合う機会が激減。
- 知識として「環境」を学んでも、自然と一体である感覚を養えていない。
👉 欠けているのは 「自然と共生する感性」
5. 「死」をタブー視する風潮
- 学校では「死」を避け、触れない。結果として子どもは死を恐れ、自殺やいじめに無防備。
- 死を学ばなければ、生もまた深く学べない。
👉 欠けているのは 「死の真実を教える教育」
6. 家庭教育の弱体化
- 家庭が「教育の出発点」であることを忘れ、学校任せにする傾向。
- 愛と信頼の土台が家庭で築かれなければ、子どもの心は不安定になる。
👉 欠けているのは 「家庭の愛を基盤とする教育観」
7. 人格より、能力を重視
- 就職や社会的評価が「学歴・資格・技能」ばかりを見て、人格や霊性を無視。
- 「優等生でも、人間性が欠けている」現象を多発させている。
👉 欠けているのは 「人格形成・魂の完成」。
8. 平和教育の形骸化
- 「戦争はダメ」と教えるだけで、戦争の根本原因=「利己心」「物質主義」を教えない。⇒結局の所、「霊的真実を知らない」に、行きつく。
- 真に平和をつくる心=「人類は霊的一家族」という自覚が育たない。
👉 欠けているのは 「霊的平和観」
9. 宗教教育の偏りと忌避
- 特定宗教を押しつける危険性を恐れるあまり、「霊性そのもの」を避けてしまう。
- 結果として、子どもは「生きる意味」「なぜ学ぶのか」を見失う。
👉 欠けているのは 「普遍的な霊的真理」
10. 教育者の使命感の低下
- 教師が「知識の伝達者」になり下がり、「魂の導き手」という使命を忘れている。
- 教師の心が疲弊していては、子どもに光を与えられない。
👉 欠けているのは 「教育者の霊的自覚」
◆ 黄輝光一的総括
現代教育は、便利で豊かになった社会に合わせ「頭と技術」を育ててきました。
しかし、最も大切な 「心・魂・霊性」 を忘れてしまったのです。
教育がこのまま「物質文明の下請け」に留まれば、子どもたちは生きる意味を見失い、いじめ・自殺・争いが絶えません。
だからこそ、次のステップとして「霊界教育基本法(教育マニフェスト)」が必要になるのです。
次回は、黄輝光一の「霊界教育基本法(教育マニフェスト)」です!!
乞うご期待!!