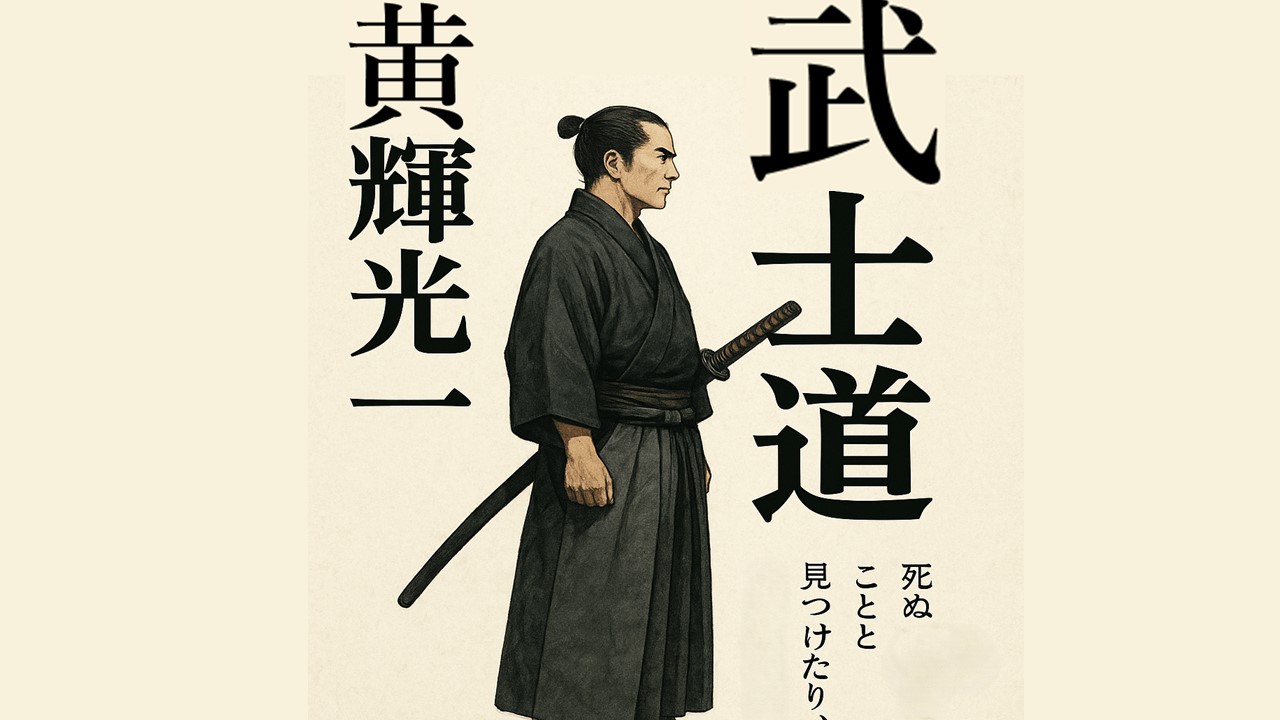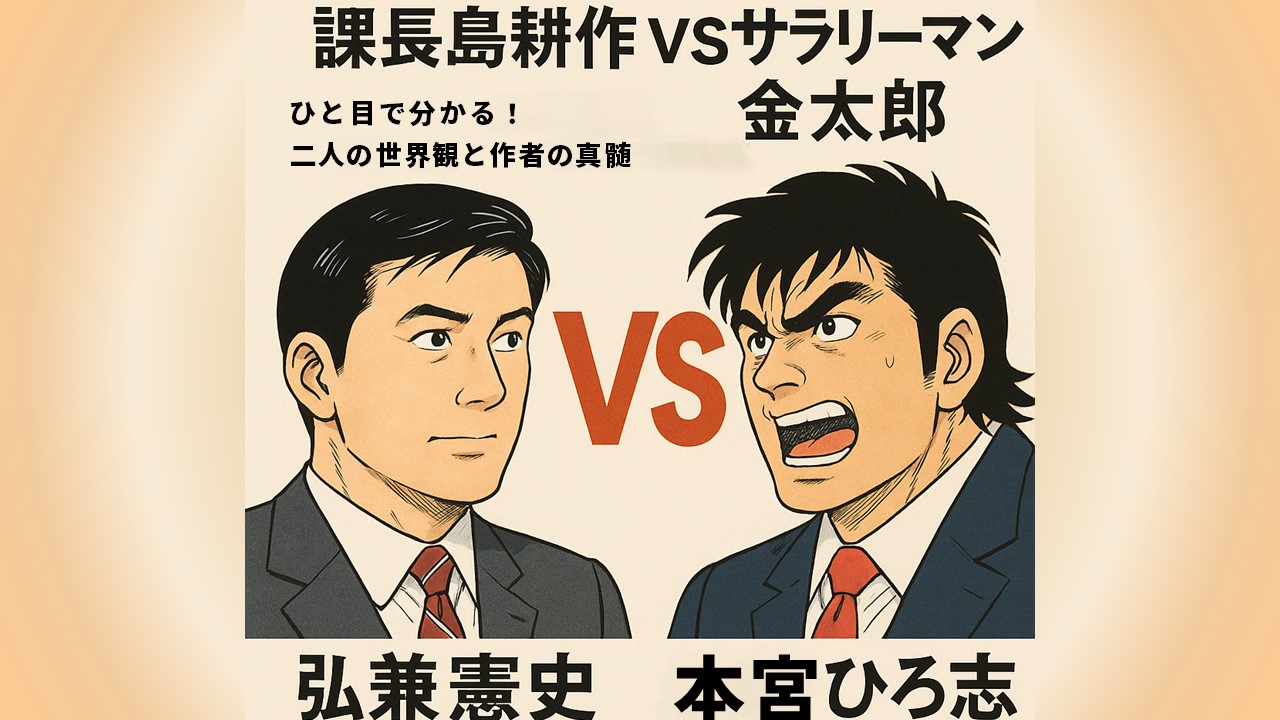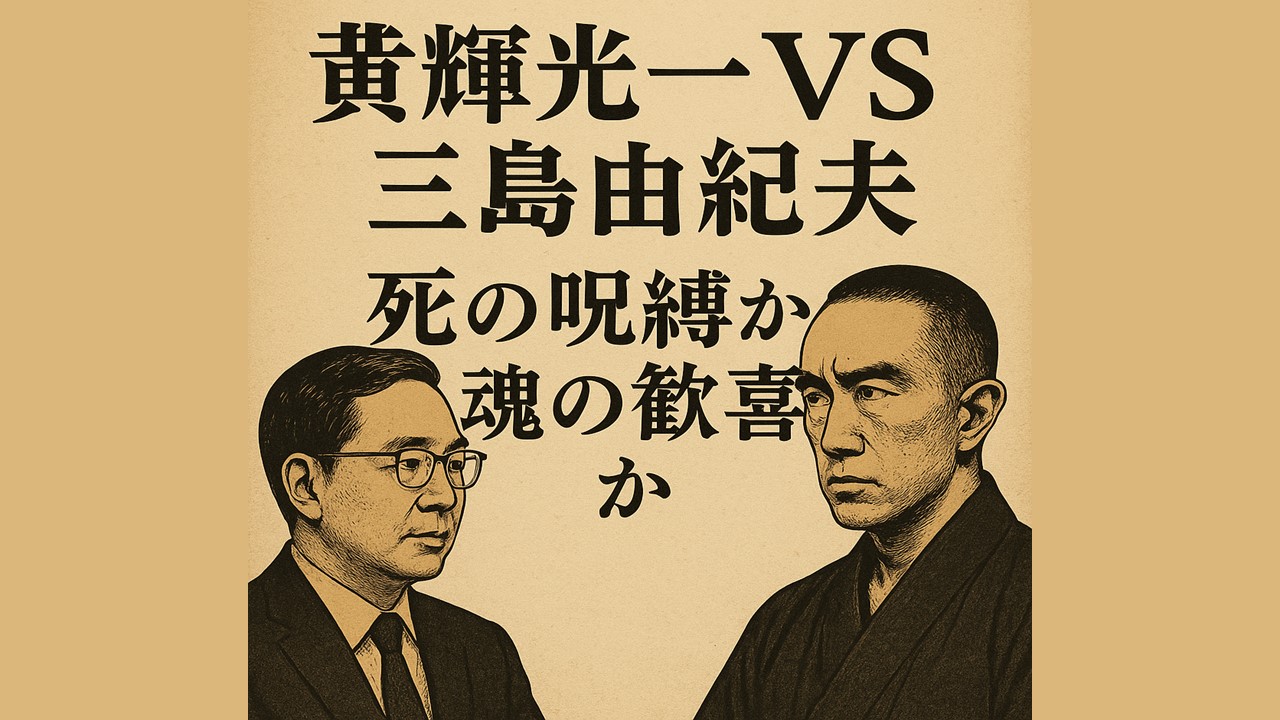序文(はじめに)
日本人の魂を形づくってきたもののひとつに、
「武士道」という思想があります。
義を重んじ、主君や国家のために命を賭ける覚悟。
その美学は、時代を超えて多くの人々を魅了し、
誇り高き精神として語り継がれてきました。
しかし、私、黄輝光一は、長い人生と霊的探究の末に、
この武士道の奥に潜む「危うさ」を感じずにはいられません。
名誉や忠義、上下関係という名のもとに、
人間は本当に自由でいられるのか?
「神の摂理」に照らして見たとき、
国家も上司もなく、
あるのは「愛と奉仕」「平等と共存」のみです。
今こそ、武士道を「愛と霊性の視点」で再検証し、
「死ぬことと見つけたり」という言葉を
「愛することと見つけたり」へと昇華すべきではないかと・・・
このVSシリーズでは、
黄輝光一 VS 武士道 という視点から、
古き良きものを活かしつつ、
人類の未来の魂の在り方を問い直す試みです。
1. 武士道とは何か
成り立ち
- 起源
平安末期~鎌倉時代に、武士階級が成立し、武士として生きる上での規範が自然発生的に形成されました。 - 江戸時代での確立
平和が長く続く江戸期に、実戦の武士から官僚・指導者としての武士へと役割が変化し、精神的・道徳的規範として体系化されたのが武士道です。
【武士道の核心】
- 義(正義・公正)
- 勇(恐れを克服する勇気)
- 仁(弱き者への思いやり)
- 礼(礼儀、調和)
- 誠(嘘偽りのない心)
- 名誉(恥を知る)
- 忠義(主君や大義への忠誠)
【新渡戸稲造の「武士道」より】
特に江戸時代は「武士の存在意義=精神性」に集約され、命よりも名誉や義を重んじる思想が強調されました。
2. 「武士道といふは、死ぬことと見つけたり」の意味
この言葉は 山本常朝の『葉隠』(1716年頃) にあります。
誤解されやすい表現
- 表面的には「死ねばよい」「命を粗末にせよ」という意味に見えますが、本意は異なります。
【真意】
- 恐怖心を克服する
武士にとって最大の敵は「死への恐怖」。
死を受け入れてしまえば、恐れなく堂々と正義を貫ける。 - 覚悟の象徴
生きるか死ぬか迷って行動が遅れるよりも、
「死を覚悟して即断即行すること」が武士道の理想。 - 無私の境地
自己保身よりも、義・忠義・名誉を最優先する心構え。
常朝は「死を選べ」というのではなく、
死を恐れない心こそが、正しく生きる勇気を生むと説いたのです。
3. 武士道の精神(現代への影響)
- 明治以降、新渡戸稲造(1862∼1933年71才没)『Bushido: The Soul of Japan』 によって、西洋にも知られるようになり、
日本人の誠実さ・礼儀・責任感の根源として理解されました。 - ただし、太平洋戦争期には「命を捨てること」のみが誇張され、曲解されました。
本来の武士道は、生きる上での品位と覚悟の道です。
☆ ☆ ☆
黄輝光一 VS 武士道(特別編)
副題:武士道とは、死ぬことと見つけたり。(葉隠)
⇒武士道とは、愛することと見つけたり(黄輝光一)
第一部 武士道の成立と魅力、そして「影」
1. 武士道という思想
武士道――。
この言葉は日本人の精神文化の象徴として、長らく語り継がれてきました。
主君に対する絶対の忠義、名誉を守るための潔さ、そして死をも恐れぬ勇気。
この三つを中心に据えた精神規範は、特に江戸時代に完成し、
多くの人の生き方の指針となりました。
しかし、この武士道は初めから理念として存在していたわけではありません。
戦乱の世を生き抜くために、自然発生的に生まれた行動規範が、
平和な江戸時代に入ってから、儒教・禅・神道の思想と融合して形づくられたのです。
2. 武士道の「美学」
武士道には、人を惹きつける魅力があります。
- たとえ弱くとも、義を貫く心
- 恐怖に打ち勝つ勇気
- 名誉を重んじる気高い態度
これらは現代人の心をも打ちます。
特に「武士道といふは死ぬことと見つけたり」という「葉隠の一節」は、
命を賭してまで義を貫く覚悟を端的に表した言葉として有名です。
3. 忠臣蔵にみる武士道
忠臣蔵――赤穂浪士四十七士の物語。
主君の無念を晴らすため、1年半の歳月を忍び、
やがて仇討ちを果たした彼らの姿は、武士道精神の象徴とされます。
この物語には、確かに仲間を信じる絆や恐怖を超えた行動が見えます。
だが同時に、復讐という名の暴力が堂々と正当化されていることも事実です。
いかなる理由があろうとも、「復讐」は、未熟なる魂です。そこには、いかなる大義もあり得ません。(黄輝光一)
4. 武士道の「光」と「影」
武士道の「光」は、
恐怖心を克服し、己を律し、義を貫く精神です。
しかし、その「影」は、
- 名誉や忠義を守るためなら人の命を奪ってよい
- 国家や主君という枠組みの中で命を捨てることが美徳
- 階級・命令・服従という構造を絶対視
こうした思想が、やがて戦争を正当化する温床となったのです。
5. 歴史が示したもの
明治以降、この武士道は国家によって再利用されました。
**「お国のために死ぬことは最高の誉れ」**という教育の中で、
多くの若者が戦場に駆り出され、命を落としました。
結果として、武士道の覚悟は、
愛の実践ではなく、戦争という悲劇に直結する力となってしまったのです。
今まさに、その危険な領域に入ろうとしている。国益。お国のために・・・
6. 黄輝光一の立場
ここまで述べたことを踏まえ、私はあえて宣言します。
武士道は、神の摂理から見れば、危険思想である。
なぜなら、地上的権威(国家・主君・上司)を絶対化し、
そのために人を殺し、自らも死ぬことを正義と錯覚してしまうからです。
これから述べるのは、
武士道を批判しながらも、その精神性を愛と奉仕へと昇華させる道です。
第二部 武士道 VS 神の摂理
1. 名誉・忠義・国家――その正体
武士道の中核を成すものは、
**名誉、忠義、そして国家(藩・主君)・天皇**です。
これらは地上の価値観としては強く響くものです。
しかし、シルバーバーチの霊訓に基づけば、
霊的価値とはまったく次元が異なるものです。
名誉
名誉は、人間の目による評価に過ぎません。
どれほど名誉を守ろうとしても、
霊界には「世間体」「評判」「勝ち負け」は存在しません。
霊界で問われるのは、
どれだけ愛をもって人を生かしたか。
名誉を守るために人を斬り殺す行為は、
どれほど勇敢に見えても、霊的には後退です。
忠義
忠義という言葉は美しく聞こえますが、
その実態は、特定の個人や集団に縛られることです。
シルバーバーチは言います。
「人間の魂は自由です。
主君に従うために生まれたのではありません。
神の摂理に従って、自分の中の神性に忠実でありなさい。」
国家
国家という枠組みは、
人間が線を引き、分け、争うために作ったものです。
霊的な世界に国境は存在しません。
愛と奉仕の対象は、人類すべてであり、
「日本人」「外国人」といった区別そのものが消え去ります。
2. 武士道の究極形=戦争
戦争とは、武士道が最後まで突き詰めた形です。
戦場において、
忠義・名誉の名のもとに多くの命が奪われます。
そこでは正義も義理もありません。
あるのは恐怖と破壊だけです。
シルバーバーチの言葉を借りれば、
「戦争は最大の愚行であり、
それを美化するいかなる思想も、人類を後退させる。」
3. 死を恐れぬ心――その力と誤用
武士道が残した最も尊いものがあります。
それは、「死を恐れぬ心」です。
この勇気は、方向を誤らなければ非常に価値があります。
問題は、その対象です。
- 主君・国家のため → 武力の道
- 神の摂理・全人類のため → 愛の道
勇気の方向性が変わるだけで、結果は180度変わります。
4. シルバーバーチが説く「本当の忠義」
バーチが説く「忠義」はこうです。
忠義とは、主君でも国家でもなく、
神の摂理への忠義である。
これは命令や服従とは無縁です。
魂の自由の中で、愛をもって人のために尽くすこと、
これが霊界で唯一尊ばれる忠義です。
5. 比較シート
要点を比較表として示します。
| 項目 | 武士道 | 黄輝光一(シルバーバーチ) |
| 絶対の対象 | 主君・国家 | 神の摂理・全人類 |
| 価値基準 | 名誉・忠義 | 愛・奉仕 |
| 死の位置づけ | 死で義を示す | 死は通過点、どう生きるかが重要 |
| 社会構造 | 上下・服従 | 平等・共存 |
| 行き着く先 | 戦争・復讐 | 平和・霊性の進化 |
6. 私の結論(中間点)
私は武士道を完全に否定するものではありません。
なぜなら、そこには人間の勇気と無私の萌芽があるからです。
しかし、名誉・忠義・国家という枠に閉じ込めた時点で、
その美しさは「危険思想」に転じるのです。
これが、私の確信です。
第三部 武士道を超えて——「武士道とは、死ぬことと見つけたり」⇒「武士道とは、愛することと見つけたり」
1. 武士道を超えるということ
これまで述べたように、
武士道は人類の精神史において大切な段階でした。
- 恐怖を克服する心
- 無私の萌芽
- 義を貫こうとする強さ
これらは、魂が幼い時代に必要な学びであり、
一歩先へ進むための土台でもありました。
しかし、その到達点である「国家のための死」は、
もはや次の時代に進むためにはまったく不要です。
2. これからの忠義
本当の忠義とは何か?
「神の摂理への忠義。
すべての命を大切にすることへの忠義。」
そこには、主君も国家もありません。
階級も命令もなく、すべてが横一線の存在として認め合う。
3. これからの勇気
勇気とは、命を賭して戦うことではありません。
勇気とは、戦わない選択を貫く強さです。
- 武器を捨てる勇気
- 憎しみを手放す勇気
- 誰かのために愛を行動で示す勇気
これらは戦場よりもはるかに困難で、
はるかに大きな価値を持ちます。
4. 死の再定義
武士道が大切にしてきた「死の覚悟」。
これは否定されるべきではありません。
ただし、方向性を変えるのです。
死ぬことを恐れないのではなく、
愛を恐れずに生きる覚悟。
命を懸ける対象を、
主君や国家から、全人類への愛へと変えること。
これが霊性時代の新しい覚悟です。
5. 新しいモットー
葉隠の有名な一節、
「武士道といふは死ぬことと見つけたり」
この言葉を、更に
私は次のように置き換えます。
「霊性の道といふは、愛することと見つけたり」
死の美学を超えて、愛の実践へ。
ここにこそ、
人類が進むべき新しい武士道=魂の道があるのです。
6. 結論
武士道を敬意をもって振り返り、
今ここで、その思想を未来へ昇華させるときが来ました。
- 忠義 → 摂理への忠義
- 名誉 → 愛の実践
- 死ぬ覚悟 → 愛する覚悟
これが、
**「黄輝光一 VS 武士道」**の結論です。
あとがき
武士道は、古き日本人の魂の象徴でした。
しかし21世紀の今、
私たちはその勇気を戦いではなく、
愛と奉仕へと向けるべきです。
もう、国家も主君も要りません。
必要なのは、
ただ一つの道――愛することと見つけたり。
詩:武士道とは霊性の道なり、すなわち、愛することと見つけたり
刀を捨てよ
名誉のために
忠義のために
命を捨てる時代は もう終わった
人の価値は
何を守ったかではなく
どれだけの愛を
与えたかで決まる
恐れるな
死を恐れず
もっと恐れるべきは
愛さぬまま生きること
いま
あなたの心に生まれる
一筋の光
戦わず
傷つけず
支配せず
ただ
共に生きる
共に笑う
その道こそ
愛することと見つけたり
☆ ☆ ☆

【参考】 新渡戸稲造とは
新渡戸稲造(にとべ いなぞう、1862-1933)は、国際的に著名な教育者・思想家で、特に『武士道』(Bushido: The Soul of Japan、1899年)の著者として知られる。彼の生い立ちと思想の核心を簡潔にまとめる。
生い立ち
- 出生と幼少期
- 1862年、岩手県盛岡藩(現在の盛岡市)に生まれる。藩士の家系で、幼少期から儒学や武士の倫理に触れて育った。
- 13歳で上京し、東京英語学校(現・東京大学教養学部)などを経て、札幌農学校(現・北海道大学)に進学。ここでキリスト教に入信し、内村鑑三らと親交を深めた。
- 海外留学
- 1884年、渡米してジョンズ・ホプキンス大学で学び、さらにドイツに留学。農学と経済学を修めつつ、西洋の思想や宗教を吸収した。
- 国際人としての活躍
- 帰国後は教育家として活躍し、東京帝国大学教授や第一高等学校校長などを務める。
- 1920年には国際連盟の事務次長としてジューブに赴任し、国際平和に尽力した。
【思想の核心】
- 『武士道』のテーマ
- 西洋に日本の精神文化を紹介するため英語で執筆。武士道を「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義」などの徳目の体系として解説し、日本の道徳的基盤がキリスト教的な「宗教」ではなく「武士の倫理」に由来すると説いた。
- 武士道を「日本の魂」と位置付け、封建時代の倫理が近代化の中でも生き続けることを強調した。
- 平和主義と国際協調
- キリスト教の影響から平和主義を唱え、日米関係の改善や国際連盟での活動を通じて「架け橋」として働いた。
- ただし、晩年は軍国主義の台頭に苦悩し、日本の国際的孤立を憂えた。
- 教育への情熱
- 「世界市民」の育成を目指し、教養教育や人格形成を重視。『修養』などの著作で自助努力の精神を説いた。
後世への影響
- 『武士道』は海外で広く読まれ、日本文化理解の古典として今も参照される。
- 新渡戸の思想は、伝統的倫理と近代的価値の融合を模索した点で、現代の日本的アイデンティティ論にも通じる。
彼の生涯は、「日本的精神の国際的発信」と「東西文化の調和」を体現したものと言える。
以上。

釼を捨てよ、心に釼(覚悟)を持て