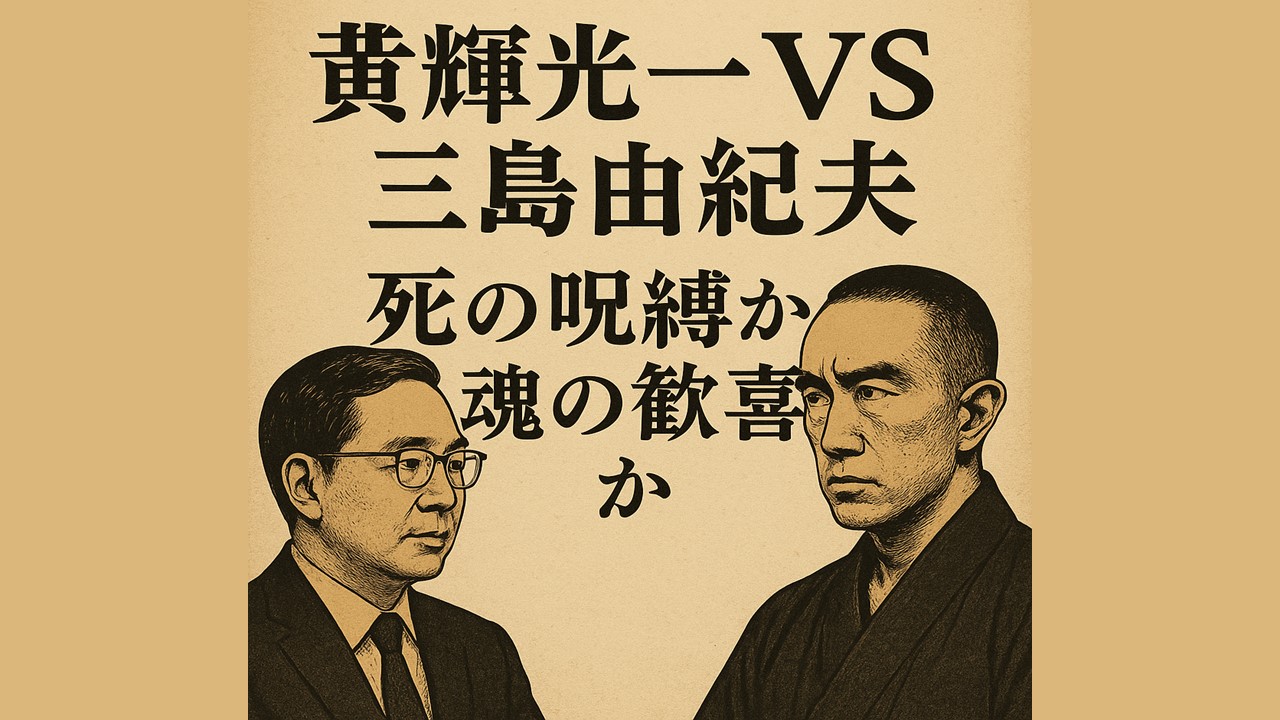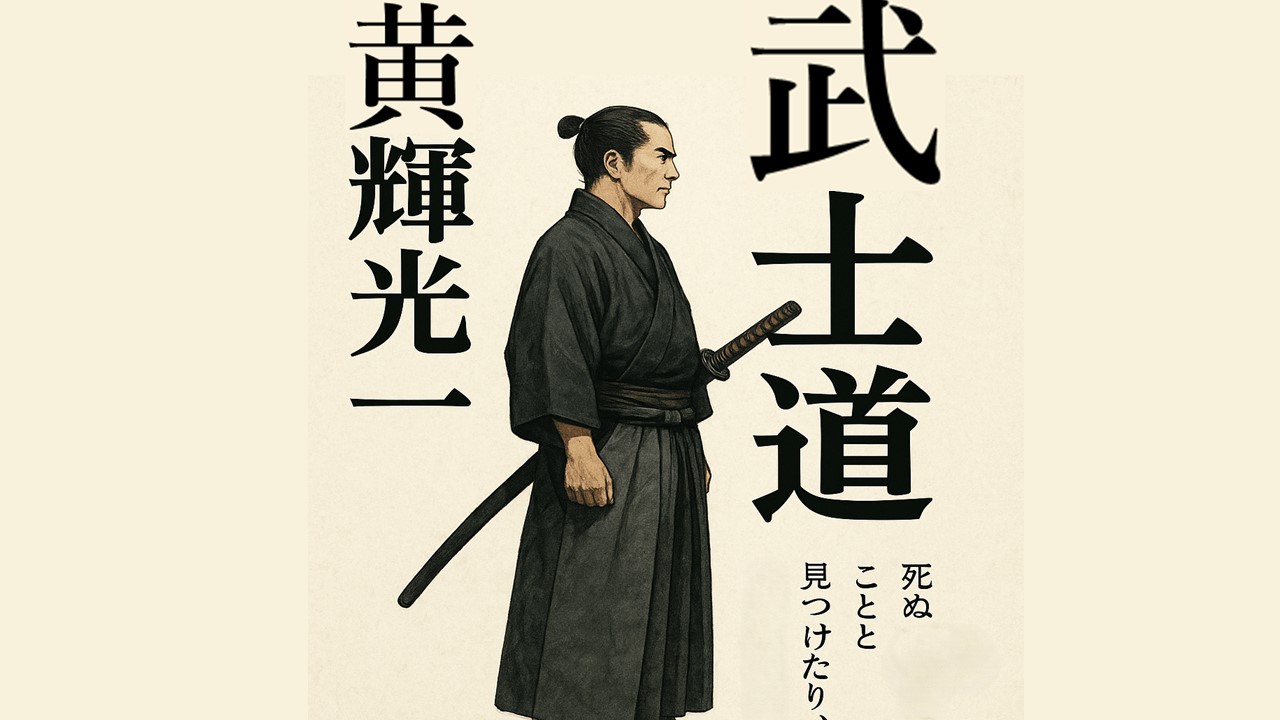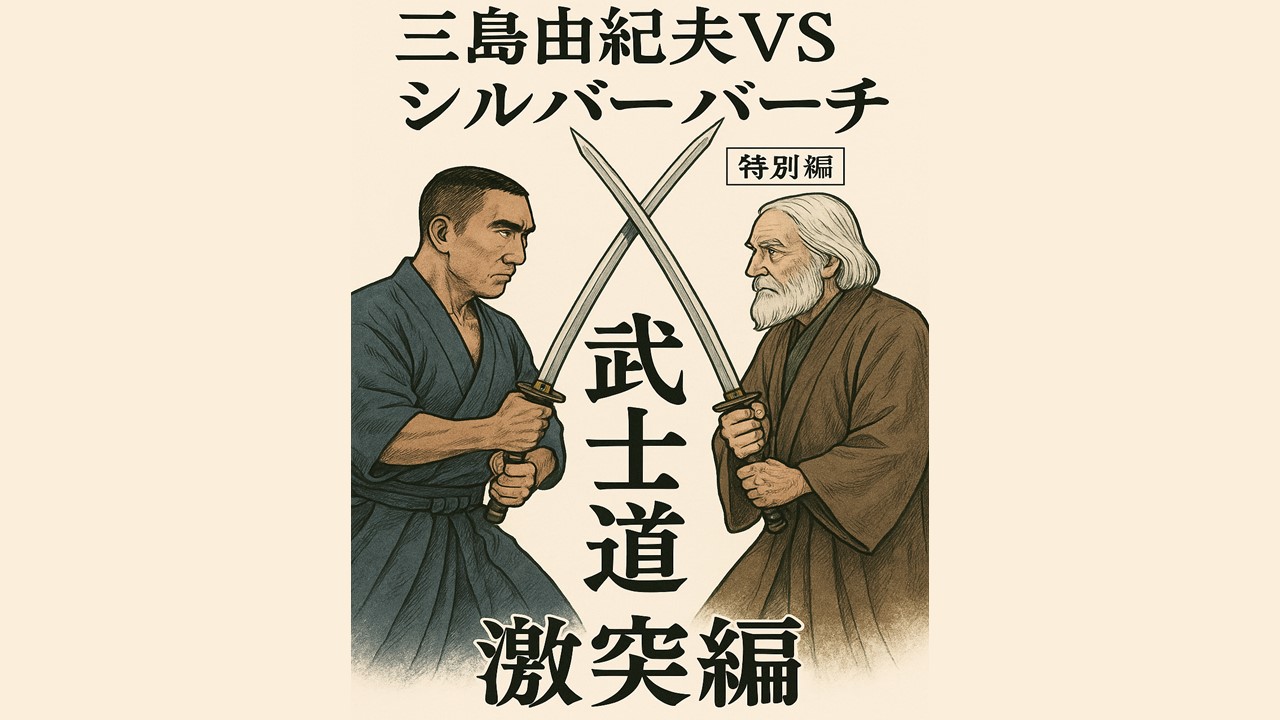【序曲】
🥀1.三島由紀夫の「死生観」──その骨格とは?
◎核にあるのは、《死=美》という観念
三島にとって「死」は単なる終焉ではなく、生の完成、美の極致、理念の実現でした。彼の名言の一つにこうあります。
「生きながら死ぬことを覚えねばならぬ」
これは禅の「即身成仏」とも共鳴しますが、三島の場合はもっと肉体的で劇的な響きを持ちます。
三島由紀夫は、45歳で自死。市ヶ谷の自衛隊駐屯地にて割腹自殺。
⚔️2.死に至る美意識──「葉隠」に憧れた三島
三島は、江戸期の武士道書『葉隠』に強く影響を受けており、そこにある「武士道とは死ぬことと見つけたり」の一文を、深く心に刻んでいました。
「死に様こそがその人間のすべてを物語る」
「死によってしか、理念は具現化できない」
このように、三島にとって死は「理念の証明」であり、逃避でも絶望でもない。それどころか、自らの信ずる「日本」「武士道」「美」「天皇」への帰依の最終形だったのです。
📘3.小説から読み解く死生観
《例1:『仮面の告白』》
彼の青年期の同性愛的葛藤、美と死の幻想を描く告白的小説。
→ 死への憧れが性的興奮と結びついており、死を「美しさ」の絶対表現」として描く。
《例2:『金閣寺』》
美の象徴である金閣に執着し、最後はそれを焼く青年。
→ 美が永遠に手に入らないなら、破壊によって永遠化するしかないという思想がある。
→ 美は「静止した死」のなかにしか実在しない、という三島独自の認識。
🌊4.『豊穣の海』四部作と輪廻観
この四部作は、
- 『春の雪』 刊行年 1969年(昭和44年)
- 『奔馬』 刊行年 1967年(昭和42年)
- 『暁の寺』 刊行年 1968年(昭和43年)
- 『天人五衰』 刊行年 1970年(昭和45年11月25日。絶筆)
全巻の執筆期間は、約5年間。刊行年が、前後していますが、それは理由あり。
物語りの流れは、同一の魂(本多繁邦が観察する若者たち)が輪廻転生していく物語です。
◎中心テーマ:
- 輪廻(Reincarnation) =「魂の永遠性」
- 肉体と精神の乖離
- 美と死の永遠回帰
- 理念は果たして実現しうるか?
◎だが…最終作『天人五衰』では……
最終巻において、主人公・本多が出会う少年・透は、輪廻の記憶も意味もすべて失っており、「魂の成長」や「霊性の進化」といったものが否定されるかのように描かれます。
そして本多は最後、老いにまみれ、空虚な日々のなかで死にゆく。
→ここで三島は何を言いたかったのか?
これは三島由紀夫の最大の問いと矛盾の告白でもあるのです。
「生まれ変わりも、霊魂も、救済も、本当にあるのか?」
「理想や理念、そして死でさえ、実は空虚な幻想ではないのか?」
しかし、黄輝光一は、その遺言ともいうべき第四部「天人五衰」の結末に大いに失望した。その理由は・・・
🕊️5.三島はなぜ、自決したのか?
1970年11月25日、自衛隊市ヶ谷駐屯地にて、①憲法改正・②天皇主権復活を訴えて割腹自殺。これは一種の《儀式》であり、《文学の帰結》でもありました。
彼の行為は、こう解釈できます。
- 死によってしか、生は完成しない
- 美しき理念は、現代社会では笑いものになる
- だからこそ、死によって美を証明し、永遠化したかった
💬6.結論:三島の死生観とは?
| 観点 | 三島の思想 |
| 死とは? | 美の極致。生の完成形。理念の実現。 |
| 生とは? | 不完全で、死によって完成される存在。 |
| 魂とは? | 永遠性を持つが、その意味も崩れうる(『豊穣の海』にて)。 |
| 生まれ変わりとは? | ある種の希望であったが、最後には虚無へと帰した。 |
| 理想の死とは? | 美しく、劇的で、理念を体現した死(武士道的死)。 |
| 現代社会とは? | 軟弱で、理念を嘲笑する世界。だからこそ、死が必要だった。 |
〔シルバーバーチ的視点〕
三島由紀夫の思想は、霊的真理から見ると一面的かつ偏向的です。
- 死は終わりではなく、あくまで「次の霊的人生の始まり」であり、逃避や美化すべきものではない。
- 自決や破壊的行為は、魂の成長を妨げ、輪廻において課題を積み残すことになる。
- 『豊穣の海』の結末が「空虚」で終わったのは、まさに三島が「死を終点」と誤認していた証左です。死んだらお終い。虚無に帰る・・・それは、許されざる結末である。
【黄輝光一の前振り】
「死は魂の帰還。最大の喜びである。魂は不滅であり、死そのものが、存在しない。生とは、永遠の進化・向上であり、死のそのものが、本当の自分に戻れる帰還であり、解放であり、真の自由がそこにある。それは喜びであり歓喜である。
三島由紀夫は、死というものに、捕らわれ、更には、美化し、最大の呪縛の中で、もがき苦しみ、そこからまったく脱出できなかった。
『死』の真実を知った時、三島は本当の『生』を知ることになる。その真実は、三島にとっては、受け入れがたい、絶対に肯定できない『神の真実」である。
三島は、脱出するのが極めて困難なジグゾーパズルの中にあった。
そこは(自死)、「光明の世界」ではなく、「冥府魔道」の世界である。
三島は、今まさに霊界で、先人たち(高級霊)のお導きにより、光明の世界・真実の世界の門を開け、模索している。
では、いよいよ開演致します。
🌸三島由紀夫 VS 黄輝光一
副題:美化された死 VS 魂の歓喜なる帰還
著:黄輝光一
【一】死とは何か──ふたつのまなざし
三島由紀夫にとって「死」とは、美の極致であり、理念の完成であり、肉体の美学による昇華であった。
その死には常に「劇場的要素」が伴い、観客=世間のまなざしを想定した、見せる死?であった。
一方、黄輝光一にとって「死」とは、魂の故郷への帰還であり、本当の自己への回帰であり、霊的な歓喜と解放である。
死とは終わりではなく、むしろ始まりであり、魂の永遠の旅路の一幕にすぎない。
死は決して恐れるものではなく、迎え入れるべき霊的祝祭なのだ。
【二】三島の死生観──「美しき死」への執着
三島は『葉隠』に心酔し、そこに語られる「武士道とは死ぬことと見つけたり」の精神に、自らの理念を重ねた。
『仮面の告白』『金閣寺』『奔馬』など、あらゆる作品において、「死」は美と同義であり、生は不完全な過程でしかなかった。
そして最終作『豊穣の海』四部作において、輪廻転生を主題としながらも、最終巻『天人五衰』で、その回帰すらも空虚な循環として放棄した。
『理想はこの世界に実現されることはない。
だからこそ「死」によって理念を証明せねばならない──』
――それは、三島の絶望的美学である。
だがその結末は、**真の救いも進化もない「虚無的輪廻」**だった。
【三】黄輝光一の死生観──「死のない世界」への覚醒
対して、黄輝光一の死生観は明確である。
「死は魂の帰還。最大の喜びである」
「魂は不滅であり、死そのものが、存在しない」
この視座に立てば、三島が渇望した「理念の証明」は、死によって達成されるものではなく、生の中でこそ実現すべきものであったとわかる。
死を美化し、そこに真実の存在を求めた三島は、もっとも重要な霊的真理──「生きながら霊的進化を遂げること」──を完全に見落としていたのである。というより、思い至らずその真理に到達しなかった。
【四】呪縛の中の三島──自死という冥府魔道
三島の死は、文学の帰結であると同時に、彼自身が創り出した「ジグソーパズルの迷宮」そのものだった。
「美しく死ぬこと」
「肉体をもって理念を証明すること」
「昭和の日本に理念を蘇らせること」
これらはすべて、**この地上世界において“限界のある手段”でしかなかった。
その死は、霊界から見れば「冥府魔道」**であり、魂の真の自由を妨げる鎖でもあった。
【五】いま、霊界にて──三島の彷徨と導き
三島は今、霊界において、高級霊たちの導きにより、**本当の「死の意味」**を学び始めている。
- 自死がもたらした魂の苦しみ
- 美と理念が、霊的真理に到達し得なかった限界
- 本当の歓喜とは「生きること」そのものにあるという覚醒
これらの課題を通じて、三島は今ようやく、真の意味で「生き直し」を始めている。
【六】結語──死に囚われた魂へ
三島由紀夫の魂は、「死」によって美を完成しようとしたがゆえに、真の生から遠ざかった。
だが魂は不滅であり、いかなる迷妄からも、やがて脱しうる存在である。
霊界では、時間は無限であり、学びの機会は永遠に続く。
三島が、自己の創り出した死の迷宮から脱し、「本当の歓喜と自由なる霊的生」を見出す日が来ることを、私は信じている。
それこそが、三島にとっての**本当の“豊穣”**であり、
そして魂の「真の海」なのだから。
🌌 美しき「たましいのシンフォニー」
―― 死をめぐる二つの旋律 ――
第一楽章 〈黄輝光一の旋律〉
死は
夜明け前の静寂
扉が開く瞬間
帰郷の汽笛が遠くで鳴る
そこには涙も恐れもなく
ただ、やさしき光があふれている
それは歓喜
それは自由
そして魂が本来の姿へ還る
永遠の旅路の、通過点
第二楽章 〈三島由紀夫の旋律〉
死は
燃える花の最期の咲きざま
剣が月光を裂く瞬間
理念は血潮に染まり
美は肉体に宿ったまま
この世の舞台で幕を閉じる
観客の喝采を背に
孤独な魂は
闇の廊下を、ただ一人進む
美のための死 それは呪縛
第三楽章 〈二つの旋律の対話〉
――「死は解放だ」
――「死こそ完成だ」
交わらぬはずの音が
ふと、ひとつの和音になる
黄輝の旋律が
三島の闇に、ひとすじの光を差し込み
三島の旋律が
黄輝の光に、緊張と陰影を与える
第四楽章 〈合奏〉
やがて二つの旋律は
霊界の大ホールで響きあう
歓喜と美
解放と呪縛
光と影
それらが渦を巻き
魂の大海原へと流れ込む
そこに「死」はなく
ただ、永遠の生の楽章が
鳴りやむことなく続いていく
【たましいのシンフォニーⅡ】
黄輝光一 × 三島由紀夫「死」
四つの楽章のための詩曲
I. 序曲 「海と刃」(Allegro maestoso)
三島:
刃は一条の光。
曇れる世に、美の最期を刻むため、
私の呼吸は舞台の幕に触れ、
命は拍子木のように、緊張を打つ。
黄輝:
海ははてなく、帰郷の水脈。
死は扉ではない、風の向きが変わるだけ。
波が引くとき、真名(まな)を呼ぶ故郷の歌、
われらは裸足で、ひかりへ帰る。
合唱:
刃と海、同じ光を映しながら、
一方は断ち、一方は抱(いだ)く。
II. 哀歌 「薔薇と空殻」(Adagio sostenuto)
三島:
薔薇は散るゆえに薔薇である。
完全は停止のなかにしか滞在せず、
いまここで凍らせよ、と私の美は命ずる。
熱が冷える刹那、形は神話になる。
黄輝:
散ることの奥で、薔薇は根に還る。
形を離れて、香りだけが永遠を歩く。
停止はない、ただ螺旋(らせん)の上昇、
脱ぎすてた空殻の内側で、春が芽ぶく。
合唱:
凍りついた美よ、
根のぬくもりを聞いたことがあるか。
III. 間奏曲 「仮面と鏡」(Scherzo leggiero)
三島:
仮面は顔より真実だ。
緊張の光沢、孤独の幾何学。
鏡は返す──「死ねば完成」という反復。
黄輝:
鏡はもう一枚ある。
肉の向こう、呼吸のさらに奥。
そこには「死の不在」という透明な余白、
笑いが生まれ、涙は塩の歌になる。
合唱:
仮面が笑えば、鏡は微笑む。
ひとは二枚のあいだで、魂に触れる。
IV. 終楽章 「帰還と開眼」(Gloria con fuoco)
三島:
私は長い迷宮を歩いた。
美の鎧は重く、理念は剣の形をしていた。
だが剣先で空を突けば、空はただ、空であった。
私は自らの神話の中で、出口を見失った。
黄輝:
門は外にはなかった。
胸の中心、静かな縦扉。
開けよ──死は帰還、歓喜の主題。
歌に還れ、光に還れ、自分に還れ。
三島:
もしや、死は舞台の最後の拍手ではないのか。
観客のいない静けさ、
そこでだけ聞こえる音符があるなら──
黄輝:
それが真の自由だ。
生は連続、死は転調。
あなたの旋律は終わらない、
ただ調性を変えて、さらに透(す)む。
合唱(全員):
死は終止形ではなく、帰還のカデンツァ。
刃よ、海に溶けよ。
仮面よ、微笑の内側で眠れ。
薔薇よ、香りとして巡れ。
そして今、
魂は歩み出す──光の五線譜を、永遠へ。
☆ ☆ ☆
🧒【三島由紀夫の生い立ち】
| 項目 | 内容 |
| 本名 | 平岡公威(ひらおか きみたけ) |
| 生年 | 1925年(大正14年)1月14日、東京・四谷生まれ |
| 没年 | 1970年(昭和45年)11月25日(享年45歳) |
| 家庭環境 | 官僚の父と、華族的趣味をもつ祖母に育てられる。幼少期は過保護で病弱。 |
| 学歴 | 東京市立永田町小学校→学習院中等部科→ 旧制第一高等学校 (首席)→ 東京大学法学部卒 |
| 職歴 | 大蔵省(短期間)→ 作家・劇作家・評論家・映画監督・俳優として活躍 |
| 晩年 | 「楯の会」設立(私設民兵・1967年10月5日発足)→1970年11月25日、 自衛隊市ヶ谷駐屯地で割腹自決(クーデター未遂) |
幼少期の病弱・文学的感受性・美意識の早熟さが、彼の死生観と創作に色濃く影を落としました。
📚【三島由紀夫の代表作品群】
✒️《小説》
| 作品名 | 発表年 | 内容の概要 |
| 仮面の告白 | 1949年 | 同性愛的内面と死への誘惑。自伝的小説。 |
| 金閣寺 | 1956年 | 美への執着が破壊へ向かう青年の苦悩。 |
| 午後の曳航 | 1963年 | 若者たちの残酷な純粋性と大人社会の対比。 |
| 潮騒 | 1954年 | 古典的純愛。伊勢志摩を舞台にした青春小説。 |
| 美徳のよろめき | 1957年 | 戦後の道徳的混乱と退廃を皮肉に描く。 |
| 鏡子の家 | 1959年 | 芸術と自己表現の矛盾と虚無。 |
| 豊穣の海(四部作) | 1969〜70年 | 魂の輪廻を描いた壮大な思想的長編。 1. 春の雪 2. 奔馬(ほんば) 3. 暁の寺 4. 天人五衰 |
合計で、長編小説34冊。短編小説25冊
🎭《戯曲・演劇》
| 作品名 | 発表年 | 特徴 |
| 近代能楽集 | 1956年 | 能の近代化。西洋劇法と日本古典の融合。 |
| わが友ヒットラー | 1968年 | 権力と美意識の矛盾を描く思想劇。 |
| 卒塔婆小町 | 1957年 | 老いと美、幻想と現実の交錯。 |
| 葵上(近代能楽集) | 1954年 | 源氏物語を能風に翻案。 |
『黒蜥蜴』 ※ 江戸川乱歩の同名小説『黒蜥蜴』を脚色。1961年・三越劇場で初演(主演 丸山明宏)⇒名探偵・明智小五郎地、妖艶なる女盗賊『黒蜥蜴』と美と知恵の対決。究極の美学対決。
戯曲は、約50件。エッセイ・評論は、35冊以上。
🖋【その他の活動】
- 映画出演・監督(『憂国』など)
- 肉体鍛錬(ボディビル)・剣道・フェンシング
- 政治活動(保守思想・皇室観の表明、「楯の会」設立)
以上。
三島由紀夫「檄文」全文(1970年11月25日、市ヶ谷駐屯地にて)
われわれ楯の会は、自衛隊によって育てられ、いわば自衛隊はわれわれの父でもあり、兄でもある。その恩義に報いるに、このような忘恩的行為に出たのは何故であるか。
かえりみれば、私は四年、学生は三年、隊内で準自衛官としての待遇を受け、一片の打算もない教育を受け、又われわれも心から自衛隊を愛し、もはや隊の柵外の日本にはない「真の日本」をここに夢み、ここでこそ終戦後ついに知らなかった男の涙を知った。ここで流したわれわれの汗は純一であり、憂国の精神を相共にする同志として共に富士の原野を馳駆した。このことには一点の疑いもない。われわれにとって自衛隊は故郷であり、生ぬるい現代日本で凛冽の気を呼吸できる唯一の場所であった。教官、助教諸氏から受けた愛情は測り知れない。しかもなお、敢えてこの挙に出たのは何故であるか。たとえ強弁と云われようとも、自衛隊を愛するが故であると私は断言する。
われわれは戦後の日本が、経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本を忘れ、国民精神を失い、本を正さずして末に走り、その場しのぎと偽善に陥り、自ら魂の空白状態へ落ち込んでゆくのを見た。政治は矛盾の糊塗、自己の保身、権力欲、偽善にのみ捧げられ、国家百年の大計は外国に委ね、敗戦の汚辱は払拭されずにただごまかされ、日本人自ら日本の歴史と伝統を涜してゆくのを、歯噛みをしながら見ていなければならなかった。
われわれは今や自衛隊にのみ、真の日本、真の日本人、真の武士の魂が残されているのを夢みた。しかも法理論的には、自衛隊は違憲であることは明白であり、国の根本問題である防衛が、御都合主義の法的解釈によってごまかされ、軍の名を用いない軍として、日本人の魂の腐敗、道義の頽廃の根本原因を、なしてきているのを見た。もっとも名誉を重んずべき軍が、もっとも悪質の欺瞞の下に放置されて来たのである。自衛隊は敗戦後の国家の不名誉な十字架を負いつづけて来た。自衛隊は国軍たりえず、建軍の本義を与えられず、警察の物理的に巨大なものとしての地位しか与えられず、その忠誠の対象も明確にされなかった。われわれは戦後のあまりに永い日本の眠りに憤った。自衛隊が目ざめる時こそ、日本が目ざめる時だと信じた。自衛隊が自ら目ざめることなしに、この眠れる日本が目ざめることはないのを信じた。憲法改正によって、自衛隊が建軍の本義に立ち、真の国軍となる日のために、国民として微力の限りを尽すこと以上に大いなる責務はない、と信じた。
四年前、私はひとり志を抱いて自衛隊に入り、その翌年には楯の会を結成した。楯の会の根本理念は、ひとえに自衛隊が目ざめる時、自衛隊を国軍、名誉ある国軍とするために、命を捨てようという決心にあつた。憲法改正がもはや議会制度下ではむずかしければ、治安出動こそその唯一の好機であり、われわれは治安出動の前衛となって命を捨て、国軍の礎石たらんとした。国体を守るのは軍隊であり、政体を守るのは警察である。政体を警察力を以て守りきれない段階に来て、はじめて軍隊の出動によって国体が明らかになり、軍は建軍の本義を回復するであろう。日本の軍隊の建軍の本義とは、「天皇を中心とする日本の歴史・文化・伝統を守る」ことにしか存在しないのである。国のねじ曲った大本を正すという使命のため、われわれは少数乍ら訓練を受け、挺身しようとしていたのである。
しかるに昨昭和四十四年十月二十一日に何が起ったか。総理訪米前の大詰ともいうべきこのデモは、圧倒的な警察力の下に不発に終った。その状況を新宿で見て、私は、「これで憲法は変らない」と痛恨した。その日に何が起ったか。政府は極左勢力の限界を見極め、戒厳令にも等しい警察の規制に対する一般民衆の反応を見極め、敢えて「憲法改正」という火中の栗を拾はずとも、事態を収拾しうる自信を得たのである。治安出動は不用になった。政府は政体維持のためには、何ら憲法と抵触しない警察力だけで乗り切る自信を得、国の根本問題に対して頬かぶりをつづける自信を得た。これで、左派勢力には憲法護持の飴玉をしやぶらせつづけ、名を捨てて実をとる方策を固め、自ら、護憲を標榜することの利点を得たのである。名を捨てて、実をとる! 政治家たちにとってはそれでよかろう。しかし自衛隊にとっては、致命傷であることに、政治家は気づかない筈はない。そこでふたたび、前にもまさる偽善と隠蔽、うれしがらせとごまかしがはじまった。
銘記せよ! 実はこの昭和四十四年十月二十一日という日は、自衛隊にとっては悲劇の日だった。創立以来二十年に亘って、憲法改正を待ちこがれてきた自衛隊にとって、決定的にその希望が裏切られ、憲法改正は政治的プログラムから除外され、相共に議会主義政党を主張する自民党と共産党が、非議会主義的方法の可能性を晴れ晴れと払拭した日だった。論理的に正に、この日を境にして、それまで憲法の私生児であつた自衛隊は、「護憲の軍隊」として認知されたのである。これ以上のパラドックスがあろうか。
われわれはこの日以後の自衛隊に一刻一刻注視した。われわれが夢みていたように、もし自衛隊に武士の魂が残っているならば、どうしてこの事態を黙視しえよう。自らを否定するものを守るとは、何たる論理的矛盾であろう。男であれば、男の衿がどうしてこれを容認しえよう。我慢に我慢を重ねても、守るべき最後の一線をこえれば、決然起ち上るのが男であり武士である。われわれはひたすら耳をすました。しかし自衛隊のどこからも、「自らを否定する憲法を守れ」という屈辱的な命令に対する、男子の声はきこえては来なかった。かくなる上は、自らの力を自覚して、国の論理の歪みを正すほかに道はないことがわかっているのに、自衛隊は声を奪われたカナリヤのように黙ったままだった。
われわれは悲しみ、怒り、ついには憤激した。諸官は任務を与えられなければ何もできぬという。しかし諸官に与えられる任務は、悲しいかな、最終的には日本からは来ないのだ。シヴィリアン・コントロールが民主的軍隊の本姿である、という。しかし英米のシヴィリアン・コントロールは、軍政に関する財政上のコントロールである。日本のように人事権まで奪はれて去勢され、変節常なき政治家に操られ、党利党略に利用されることではない。
この上、政治家のうれしがらせに乗り、より深い自己欺瞞と自己冒涜の道を歩もうとする自衛隊は魂が腐ったのか。武士の魂はどこへ行ったのだ。魂の死んだ巨大な武器庫になって、どこかへ行こうとするのか。繊維交渉に当っては自民党を売国奴呼ばはりした繊維業者もあったのに、国家百年の大計にかかわる核停条約は、あたかもかつての五・五・三の不平等条約の再現であることが明らかであるにもかかわらず、抗議して腹を切るジエネラル一人、自衛隊からは出なかった。
沖縄返還とは何か? 本土の防衛責任とは何か? アメリカは真の日本の自主的軍隊が日本の国土を守ることを喜ばないのは自明である。あと二年の内に自主性を回復せねば、左派のいう如く、自衛隊は永遠にアメリカの傭兵として終るであらう。
われわれは四年待った。最後の一年は熱烈に待った。もう待てぬ。自ら冒涜する者を待つわけには行かぬ。しかしあと三十分、最後の三十分待とう。共に起って義のために共に死ぬのだ。日本を日本の真姿に戻して、そこで死ぬのだ。生命尊重のみで、魂は死んでもよいのか。生命以上の価値なくして何の軍隊だ。今こそわれわれは生命尊重以上の価値の所在を諸君の目に見せてやる。それは自由でも民主主義でもない。日本だ。われわれの愛する歴史と伝統の国、日本だ。これを骨抜きにしてしまった憲法に体をぶつけて死ぬ奴はいないのか。もしいれば、今からでも共に起ち、共に死のう。われわれは至純の魂を持つ諸君が、一個の男子、真の武士として蘇えることを熱望するあまり、この挙に出たのである。三島由紀夫
【檄文のキーポイント】
三島由紀夫が自決当日(1970年11月25日)に陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地で配布した「檄文」は、その思想的遺言として戦後日本への痛烈な批判と行動の正当化を記した文書です。以下に内容の核心を5項目で要約します。各ポイントは原文の論理に沿い、三島が最も訴えたかった問題意識を抽出しました。
🗾 1. 戦後日本の精神的退廃への批判
「経済的繁栄にうつつを抜かし、国の大本(歴史・伝統)を忘れ、魂の空白状態に堕ちた」と指摘。政治は保身と偽善にまみれ、国家の根幹が外国(主に米国)に委ねられ、日本人自らが歴史を冒涜していると断じた。
⚖️ 2. 自衛隊の「違憲性」と欺瞞の糾弾
「自衛隊は法理論上、明らかに違憲である」と断言。政府が「御都合主義の法的解釈」でごまかし、「軍の名を用いない軍」として存在させることが、日本人の道義頽廃の根源だと主張。この矛盾が「国の不名誉な十字架」だと批判した。
🛡️ 3. 「護憲の軍隊」というパラドックス
自衛隊は「国軍」としての建軍の本義(天皇を中心とする歴史と伝統の防護)を否定され、「憲法を守る軍隊」という自己矛盾に陥っている。さらに英米の「シビリアン・コントロール」(文民統制)が財政管理であるのに対し、日本のそれは人事権まで掌握され「政治家の党利党略の道具」と化したと痛罵した。
🇺🇸 4. 自衛隊の「アメリカ傭兵化」への警告
沖縄返還を控え「真の自主的軍隊となるにはあと2年しかない」と警告。この機を逃せば「左派の言う通り、自衛隊は永遠にアメリカの傭兵となる」と予言。核停条約や米中接近(ニクソン訪中)を念頭に、日本の防衛自主性の喪失を危惧した。
⚔️ 5. 「生命以上の価値」としての日本精神の覚醒呼びかけ
「生命尊重のみで魂が死んでもよいのか」と問い、軍隊の存在意義は「生命以上の価値」にあると主張。その価値とは「自由や民主主義ではなく、日本の歴史と伝統」であると規定。自衛隊員に対し、「憲法に体をぶつけて死ぬ真の武士」として立ち上がるよう訴えた。
💎 結び:三島の核心的メッセージ
檄文は「自衛隊への愛」を動機としながら、その覚醒を促す「殉死の誘い」でもありました。彼が「見せてやる」と言った「生命以上の価値」とは、天皇を頂点とする歴史的連続性としての「日本」そのものでした。
しかし、その主張は自衛隊員の罵声とヤジに阻まれ(「バカヤロー! おりてこい!」)、約10分の演説後、三島は総監室で割腹自決。その行動は「論理的矛盾を突き詰めた先の死」として、今も解釈の分かれる戦後史の象徴となっています。
以上。
【参考】
1. 「楯の会」の正確な発足日
- 1968年10月5日
三島が防衛庁(現・防衛省)で記者会見を開き、民間防衛組織としての「楯の会」結成を発表しました。
会員は当初、全国の大学生を中心に数十名規模でスタート。目的は「日本の伝統と文化を守り、国防精神を涵養する」ことでした。
2. 1967年の単身・体験入隊
- 期間:1967年4月12日〜5月27日(46日間)
これは事実です。- 場所は陸上自衛隊・東部方面隊管区の駒門駐屯地(静岡県小山町)。
- 当時はまだ楯の会は存在せず、三島個人の希望による体験入隊。
- 陸曹候補生とほぼ同じ訓練を受け、射撃・行軍・体力訓練などの記録が残っています。
- この経験が、後の『英霊の声』『わが友ヒットラー』や「楯の会」構想につながったとされます。
3. 「楯の会」としての自衛隊入隊経験
- 初回:1969年9月24日〜9月30日(7日間)
- 陸上自衛隊市ヶ谷駐屯地(当時の防衛庁本庁)および富士学校等で、楯の会会員約34名が訓練参加。
- 三島ももちろん同行し、基本教練・射撃・行軍訓練を受けました。
- 2回目:1970年10月(正確には決起直前)
- 自決事件の約1か月前に、短期間の訓練を実施。期間は2日間程度で、ほぼ最終確認的なものでした。
年表まとめ
| 年月日 | 内容 | 期間 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1967/4/12〜5/27 | 三島単身で駒門駐屯地に体験入隊 | 46日間 | 楯の会発足前 |
| 1968/10/5 | 「楯の会」発足 | — | 防衛庁で記者会見 |
| 1969/9/24〜9/30 | 楯の会として初の自衛隊体験入隊 | 7日間 | 会員約34名参加 |
| 1970/10頃 | 楯の会としての短期訓練 | 約2日間 | 決起前の最終準備 |
以上。