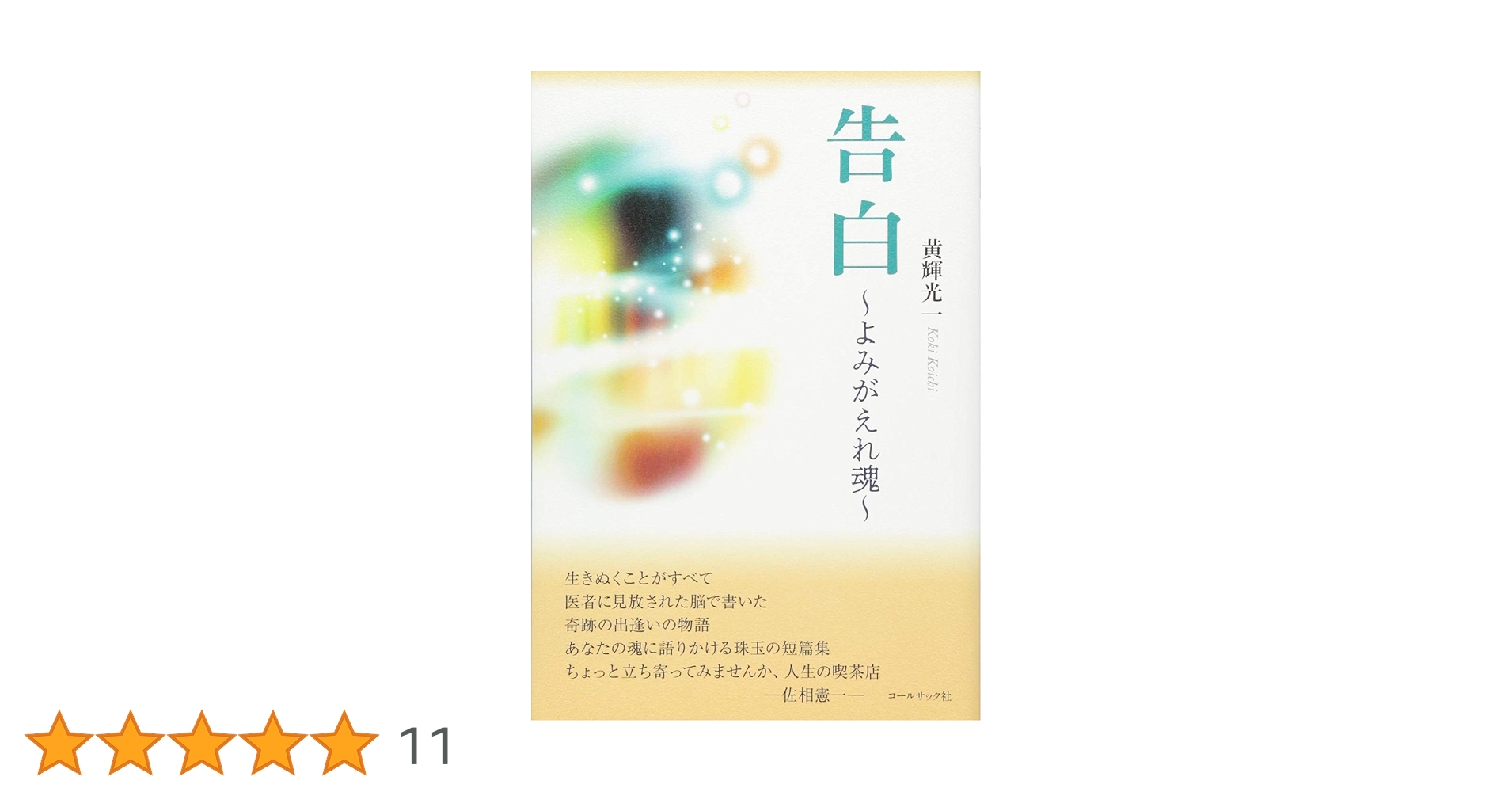〈解説者:佐相憲一〉
生きぬくことがすべて
医師に見放された脳で書いた
奇跡の出会いの物語
あなたの魂に語りかける珠玉の短編集
ちょっと立ち寄ってみませんか、人生の喫茶店
この帯文からさらに突っ込んで書いてみましょう。
この物語の出どころは、不死鳥の生死感覚を体験中の脳髄です。著者・黄輝光一(ペンネーム)は川崎に住む善良で快活な勤勉市民ですが、脳梗塞で三度倒れたところから、作家のへ道が始まりました。55歳の時に一度倒れ、65歳の時に2度。1回目の時には、それまでの突っ走ってきた人生を振り返り、節制への道は大いなる内省につながったようです。2回目、3回目と立て続けに襲った死神は皮肉なことに、文学の神に彼を預けたので、ボロボロになった作者の脳に、創作せよというメッセージが送られたのでした。いまから二年前のことです。恐るべきことに、それからあっという間に、ここに収録された10篇が書かれたというわけです。
脳梗塞なら世に体験者は少なくないでしょう。しかし、225ページにあるMRA画像を突き付けられた著者は医者に宣告されました。血流が映っていない、血管がボロボロだ、イチかバチかの緊急手術をしなければすぐに死ぬだろう。仮に手術で死んだとしても医師のせいではない、もう末期的状態と宣告されたのです。なんとその時、作家、黄輝光一が誕生しました。彼は手術を受けませんでしたが、もう二年も経っています。そしてなぜか元気に日常を暮らしています。川崎臨海部に近い京浜工業地帯の慣れ親しんだ土地の庶民的な住宅街で、愉快な妻とマンションに居住し、巣立っていった二人の娘の幸せを常に願いながら、寝たきりにもならず、小説などを創作しているのです。この状況には一流の医師たちも首をかしげます。信じられない!彼がピンピンしているなんて。センセーショナルな比喩表現を使うなら、特に左脳は無いように見えますし、本人いわく「私はゾンビ」状態です。
これをスピリチュアルな超自然現象と呼びたい向きをあるでしょうし、新興宗教の神にだってなれるかもしれません。もし彼がテレビにでも出演している俳優か歌手ならば、スポーツ新聞や週刊誌が大騒ぎして、〈死んだはずが生きている〉彼を好奇の目で報じるでしょう。セカンドオピニオンだった受けました。彼の脳は、どうしてその状態で手足が通常の動きをするのか、しかもどうして文学まで書けるのか、ゴーストライターも代筆者もなしで小説なんか書けるのか、この世の誰も科学的に説明できない領域を生きています。
現に、ローカル線で川崎大師の近くの駅で降りたわたしを自宅で迎えたのは、ラップダンスさえ見せる超陽気な紳士と、彼を励まし愛してやまないこれも超陽気な素敵な夫人・京子女史でした。そして、笑顔でいきなり見せられたのは「生前葬」の写真やすでに用意してある「遺影」その他です。ブラック・ジョークではないところがなんともブラック。泣くに泣けません。思わず、夫婦と共にわたしも笑ってしまいます。ケセラセラとかセ・ラウィとか言ったラテンのノリが、こころの奥を泣かせるようです。
そんな作者の脳が発したからこそ、収録された物語はいずれも、生きていることへの不思議な縁と〈出会いの奇跡〉、どんでん返しに満ちた人生の味わいを醸し出しているのです。それらが架空の感じを与えないのは、作者自身の実生活が、涙涙の感動軌跡と不思議なめぐり逢いに助けられてきたからでしょう。特に男女の物語が光るあたり、奇跡の脳はかなりのロマンチックです。今にも命がこと切れるかもしれない一瞬一瞬を生きていると、他者の恋愛事情にも途方もなく優しさをもつのでしょう。もちろん、生来の作者の恋愛観や人生観が反映してもいるのでしょうが、それだけではなく明らかに、収録物語に共通するせつないまでの愛の燃焼は、生死の境にいる存在そのものがためらいなく書かせたものでしょう。ここに、この本の一番の光を見ます。60年以上生きて初めて書いた文芸作品ゆえに、筆の粗さや幼い表現を指摘されるかもしれませんが、はっきり言って、それを上回る切実さと尊さを感じさせてくれます。巷に出回っている小説家が書いたものよりも魅力的かもしれません。
(人生の喫茶店)
たとえば、冒頭の収録の「白樺のハイジ」は、著者の郷里でもある長野県が出てきますが、(琥珀色の小さな喫茶店)が出会いの場所です。歳月を経て登場人物の恋はどうなったでしょうか。喫茶店の窓から白樺が揺れるのが見えるようです。
たとえば、二部構成の「踊り子」はストリッパーと元同級生、父と娘の人間ドラマですが、歳月を経て苦しいばかりの人生模様は、新宿歌舞伎町の喫茶店も舞台にしてどう展開していくでしょう。
たとえば、肉食動物である人間の心の矛盾を企業社会の中で描く「動物たちに愛を!(ベジタリアン部長)」、宝くじをめぐって生きることの考察がさりげなく描かれた「青年の苦悩(もし10億円当たったら)」スター俳優の栄光の影にあるものを守護霊の物語に描いた「守護霊の涙(ハリウッドスターの大罪)」、これらは直接的には喫茶店とは関係ないように見えますが、物語の深い所で著者が願いを込めて描いている現実心理は、突っ走っている渦中の職場や生活場所よりは、人知れず立ち止まって内省する場所、たとえば居酒屋や静かな喫茶店のような場が象徴として似合うでしょう。「占い師 銀子」でしゃれた男女の会話が交わされるラウンジバーもまたその一つです。
〈あなたの魂に語りかける〉。
この親しみ深いトーンもまた、作者の持ち味です。彼の実人生は企業競争のなかを必死に働いて食いつないで来た、ハングリーな開拓者でした。しかし、だからこそ、そのなかでの内省は、一番大切なものとしての愛する家庭、トップ級の腕をもつ囲碁など人々との交流世界、といった方向を志向していったのでした。そこへ、生死の境を生きざるを得ない病との遭遇があって、この傾向が加速されたのでしょう。だから、彼の発する文章には、本当に魂の奥から出てきた、他者への語りかけの心がいつもあるのです。早稲田大学を出て金融や保険関係の世界を生き延びた人物が、それよりももっと大切なものにずっと気づいていて豊かな人生を生きてきたこと、そしてそんな人に限って大病に倒れる不幸を味わったこと、でもそのことからついに作家になったこと、この本の背景が文体にも濃厚に反映しています。この世のさまざまな苦しみを生きる人びとの気持ちがわかるのは、彼自身がそのなかの一人だからでしょう。特に、比較的長い二つの作品「踊り子」「占い師 銀子」は、こうした黄輝光一氏の文体が光る力作物語でしょう。
前半の創作に続いて、本の後半には、作者その人が実人生のまま登場する実話が収録されています。エッセイのような物語、あるいはドキュメンタリーもあります。「夏のセミ(ぴんころ地蔵)」「人類への警告(10万年後の世界)」「《死ぬ死ぬ詐欺》」「最終章 告白(本人)」と続きます。特にラストの二篇は、さきほど紹介した作者の実情が実況中継的に刻印されていて臨場感に圧倒されます。そして、こんな人が現実にいま生きていて、本まで出版して、物語を書いているということに、励まされる人は少なくないでしょう。
『告白~よみがえれ魂~』
この本のタイトルは、このような数奇の人生を生きている著者自身のことも表わしていますが、収録の創作小説それぞれの登場人物のありようをひとことで表現したものでもあります。それぞれに苦悩しながら、登場人物たちは大切なものを告白していきます。そして、停滞することも多々あるだろう魂が、よみがえる時間を迎えるのです。さらにこのタイトルは、世にひろく読まれるべき大切な現代メッセージとして、おそらく万人に向けられているでしょう。読者それぞれの心の奥の物語が、ここに告白された創作と実話それぞれに大切なものと深い所でリンクして、読者の魂もまたいっそうよみがえれ。そんな願いがこめられているのでしょう。
あっ、川崎の喫茶店にまた黄輝光一氏がやってきました。この夏の猛暑をもろともしないで、眼鏡に満面の笑みを浮かべて腰の低い温和な人格そのままに、この豊かな本が世にはばたく直前のゲラを手にもって……。 やあ、黄輝さん、いよいよですよ。

『告白~よみがえれ魂~』出版にあたって、多大なるご尽力を賜りました編集者、佐相憲一氏(現在、日本詩人クラブ理事長)の詳しいプロフィールはこちらをご覧ください。
一般の方々の読後感想は、Amazonレビューをぜひご一覧ください。